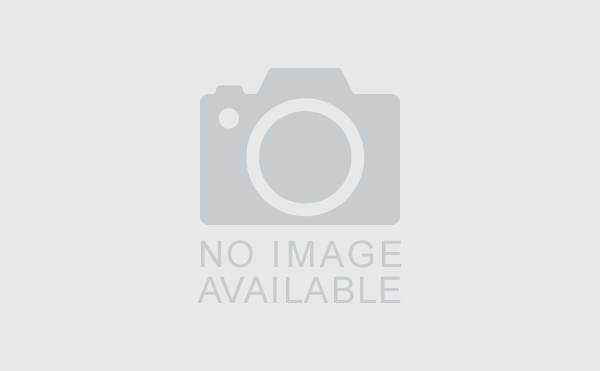紹介『長門本平家物語の新研究』
川鶴進一「『長門本平家物語の新研究』が拓く基礎的研究の新局面」
好評発売中の『長門本平家物語の新研究』(2024年10月刊)。本書刊行にあたり、川鶴進一氏(早稲田大学本庄高等学院)に、紹介文を寄せていただきました。
『長門本平家物語の新研究』が拓く基礎的研究の新局面
川鶴 進一
本書が扱う長門本は、諸本が複雑に展開する平家物語にあって最多の伝本を擁する。現存確認できた伝本は、本書が最新の成果で、その数79。『平家物語大事典』(東京書籍、2011)「長門本」項を担当した筆者が、松尾葦江氏の論考に基づき71本と記してから13年を経て、さらに8本加わったのは特筆すべき研究動向である。以下、10名による13編が並ぶ本書について、互いに連関しあう構成も確認できるよう、各編の稿者・題名も含めその概要を順次紹介する([1]~[13]は筆者による通し番号を示す)。
[1]松尾葦江「長門本とは何か」
編者による本書の序論に当たる論考。松平定信による長門本転写依頼([9][10]の紹介。以下、通し番号のみで示す)から「公的な」転写の際の副本作成も屡々だったかと推測、副本は藩校立教館に入ったはずで([8][11])、国学者、知識人、幕末の志士たちの間で、長門本を史書として写し、読むことが頻りに行われたようだと享受の様相に触れ、あわせて長門本の「善本」と「校訂」への注意を促す。現存伝本の相互関係については、定信依頼による長州藩作成本の転写本(神宮本)と、川北本(石水博物館本)とその転写本(宮書弘化二年本)とが繋がり、黒川本とその透写本(三田本)が繋がっていく究明例を示す([8][10][11])。旧稿(『軍記物語論究』〈1996〉所収)で述べた多様な本文が浮遊していた時代にも言及。現存しない、過去の長門本の姿に関連し、「原「読み本系」平家物語」「原「平家物語」」(いずれも「原平家物語」ではない)という見通しの提示は注目されよう。長門本の特色を前代の文学を引きたがる傾向ほか9つを挙げた上で、広範囲の読者層に向けた娯楽性と多少の教訓性とを志向した本と位置づける。
[2]水野直房「重要文化財平家物語長門本 戦災焼損修復の記録」
1948年、新制中学1年の水野氏は、赤間神宮宮司となった父とともに被災した旧国宝本を見て衝撃を受けた。それから約1年半をかけた修復の経緯を記す。本書刊行は、2025年に安徳天皇八百四十年先帝祭、満150年を迎える赤間神宮の記念でもあるという。2024年に卒寿を迎えた水野氏の感懐も感じられる。カラー口絵に書影紹介あり。
[3]佐々木孝浩「大内文化と「阿弥陀寺本平家物語」」
大島本源氏物語の再定位を進める佐々木氏による、大島本と阿弥陀寺本を関連づける論考。まず、阿弥陀寺本の書誌について、各冊の不統一が目立ち、大半は稚拙な筆跡とし、貴重だが偶像化すべきでないと指摘。続いて、大内氏時代の長府の重要拠点であった長福寺(現功山寺)から7km足らずの阿弥陀寺も長府文化圏にあり、永禄7年(1564)の大島本補写は長府文化圏で行われたのは確実で、阿弥陀寺本の書写時期に近いと思われること、長門一宮住吉神社の大宮司家山田家と、同二宮忌宮神社の大宮司家竹中家の人々が、阿弥陀寺本書写者の有力候補になること、さらに、阿弥陀寺本巻19は世尊寺流風の書、同巻18は書風の共通する大島本補写冊「藤裏葉」と書写下限(永禄7年頃写か)も同じであろうこと等を旧稿の再確認も交えて指摘する。作品を超えた文化ネットワークを作る長府文化圏の提言は、大いに注目される。
[4]小井土守敏「長門本平家物語の室町物語的性格」
長門本の「遊女」16例のうち、延慶本にない6例の分析を中心に行い、横笛や髑髏尼の説話を先行研究を活用して巧みに分析を加える論考。長門本の物語的性格に、①名もなき遊女に個別の物語を背負わせる、②エキストラ的存在にも物語を与え、そこに小さな山場を作る、③熟した表現、常套的表現と典型的展開による脚色で構成する、④平家物語の進行断絶よりも小さな物語を語ることを優先する、といった傾向があるとする。「遊女」の用例に「遊君」「遊び者」、(遊女と同義の)「君」を含めることや、横笛や髑髏尼の説話について、管理・背景とは距離を置きつつ、その表現のありように室町物語的性格を剔出すること等、物語分析の手法も参考になる。
[5]浜畑圭吾「長門本平家物語研究史」
伝本調査、諸本関係、成立、文学的評価、の4章に分類し、長門本研究の流れを俯瞰できる貴重な論考。多くの先行研究を確認できる82に及ぶ注も含め、多岐にわたる論文を取り上げる。細目の研究史やまとめがある論文を紹介する点も有難い。随所に氏による研究課題への重要な指摘や意見を示す所があることも見逃せない。特に、長門本と大内氏文化圏との関わりは、「文化圏」という便利な言葉に落ち着つかせず、その「時」「場」をより明確すべきとの指摘、岡山大御筆本が毛利綱元の姻戚関係による書写であるとの再確認(注9)、大隅正八幡宮管理説話の背景を追究した栗林文夫、筒井大祐の2氏の指摘をさらに検討すべきとの言及(注53)等は示唆に富む。
[6]松尾葦江「長門本平家物語伝本一覧(補遺・新出伝本)」
氏の編著書掲載の長門本伝本に新出本を加えた伝本一覧。『平家物語論究』(1985)掲載64本(通し番号1~64)、『海王宮』(2005)掲載7本(65~71)に、私家版科研報告書掲載2本(72・73)の詳細情報、新出6本(74~79)や補遺情報を加え、計79本を提示する。特に新出6本は大谷・平藤・塩村3氏による書誌で詳細が紹介される([7][8][10][11]とも関連)。計17本のWEB画像公開情報や本書対応ページを提示する備考も便利である。できれば澤本に関する大谷論文(2019)も注記があると良かった([5]で確認できるが)。また、「新たに伝本調査を始める人のために」の項目で、「研究者のための指針」「調査に着手する際の入り口と、およその方角」を、①旧蔵者・伝来、②書誌・体裁、③本文の様相の3つで示し、その具体的な方法も提示している。
[7]平藤幸「萩明倫館旧蔵長門本について」
山口大学本巻3~巻20の18冊と、近年発見の鶴見大学本巻1・2の2冊は元々揃いで、萩明倫館旧蔵本に相当することを旧稿(関西軍記物語研究会編『軍記物語の窓 第五集』〈和泉書院、2017〉所収)で論じた平藤氏による、「旧稿の要点に若干の補正」を加えた論考である。その要点は、[6]の鶴見大学本の書誌(平藤氏執筆)と照合する必要はあるが、大変な労作であった氏の旧稿とほぼ重なる。萩明倫館本について、松尾氏の指摘(『軍記物語原論』〈笠間書院、2008〉第二章第四節)を踏まえ、長門本伝本中の初期の姿を留めつつ、「改変の意欲と不完全さ」を併せ持つ長門本の本性を表す本と位置づけた。カラー口絵の書影紹介あり。
[8]大谷貞徳「三田葆光写長門本と黒川家旧蔵長門本について」
三田葆光(さんだかねみつ)が師の黒川真頼が蔵する古写本(黒川本)を1901年に透写した本が三田本である。2022年発見され赤間神宮所蔵となった。本論では、葆光の事績と人脈を紹介し、葆光筆「附録」の書誌情報から宮書弘化二年本=松浦伯爵家蔵本と指摘。三田本の成立を真頼識語から探り、関東大震災で焼失した黒川本の姿を知ることができる貴重な伝本で、山田孝雄『平家物語考』や国書刊行会本凡例に見える黒川本のいずれとも異なる伝本と推測した。三田本の長門本伝本内での特徴としては、本文は九大本を含む有序C系本のグループに近く、異本注記は早大二〇冊本や宮書弘化二年本のような伝本によると検証する。最終的に、黒川本と同じ本文をもつ三田本の資料的価値を明らかにした。カラー口絵の書影紹介あり。
[9]村上光徳「『長門本平家物語』流布の一形態」
1976年初出論考の再掲。赤間神宮第五二号書簡から、旧国宝本は簡単に書写させない重物で、老中稲葉正則の指示で門外不出になったこと等を、『国史館日録』の記事から、『本朝通鑑』編纂資料のために旧国宝本を江戸に運んで書写した後に五二号書簡を添えて下関へ返送したことを、それぞれ明らかにした。この本は次第に有名になり、閲覧書写希望者が長州藩や長府藩、両毛利家に頼み込んだであろうこと、両毛利家には旧国宝本の写しがあったことを推測する。また、山口県文書館蔵の2つの往復書簡より、定信の所望、江戸詰の長州藩家老と国元の家老のやりとり、下役同士の細かい打合せ、書写後のやりとり等、長門本書写の過程も明らかにする。資料発掘の業績は今なお重要で、文書に新たに付された松尾氏の補注([10]が関連)も大変参考になる。
[10]塩村耕「松平定信と長門本『平家物語』」
長門本に関する新出資料である塩村氏蔵松平定信書簡の写真と全文翻刻(カラー口絵の部分紹介あり)、および[9]紹介資料類等の略書誌の報告である。[9]紹介の定信の長門本書写依頼の2つの往復書簡と勘案すると、塩村氏蔵書簡は寛政5年(1793)10月のものである可能性が高く、そうだとすれば同年7月の定信の老中失脚直後となり、その内容に相応するという。[9]紹介文書3件の再調査報告では、文書全文翻刻によって全体像が把握しやすくなり、付けられた注も示唆に富む。赤間神宮、山口県文書館、石水博物館蔵の平家物語諸本の略書誌は[6][8]と照合でき、参考になる。
[11]大谷貞徳「長門本『平家物語』伝本関係の一推論」
津の豪商川喜田遠里と伊勢山田の画家正住弘美との長門本についてのやりとりを、青山英正「伊勢の文化的ネットワークと『春雨物語』の流通」(『雅俗』18、2019)に拠りつつ考察する。正住が遠里蔵本を借覧して2つの写本を作り、そのうち佐々木弘綱が入手した一本を宮書弘化二年本とした。続いて、神宮本の序文を取り上げ、松平定信の阿弥陀寺本書写依頼により、その写本が白河藩校の立教館に下され、それを密かに書写したものが神宮本とする。定信没後の白河藩主の桑名移封に伴い、白河立教館蔵書も桑名藩が新設した藩校立教館に移され、関係者に立教館蔵本を書写できる環境が生まれたこと、神宮本異本注記から伊勢に川喜田本が広まっていたことを指摘する。松阪の蔵書家小津桂窓の遠里宛書簡から、天保末年頃から伊勢で長門本が盛んに書写されていたこと等も推測する。資料を博捜された大変学ぶことの多い論考で、特に青山論は長門本流布を知る上で必読ながら、論題では長門本に結びつかず、本論によって知り得た。本書他論考(特に[5])にも共有されるべきだったと思う。
[12]伊藤悦子「長門本『平家物語』関連の記事対照表」
使いやすい記事対照表4点を挙げ、①長門本の底本、②対照できる本、③表の特徴、使用上の注意点について整理する。長門本を中心とした三本記事対照表を掲載する髙橋伸幸『長門本平家物語劄記』(名著刊行会、1975)も取り上げる対象に加えるべきではと個人的に学恩を蒙った身として思う。
[13]松尾葦江「長門本平家物語研究の回想から歩き出す」
松尾氏のブログ連載「回想的長門本平家物語研究史」(2021年7月~2022年2月の全17回)に基づきつつ本書刊行の前提を述べる。後半部からブログ内容の割愛や差し替えが増え、氏の現在の見解を踏まえた内容になっている。特に、(4)の公的写本・私的写本、(7)の大内氏文化圏との関わり、に触れる部分は割愛されており、氏の見解の変更点([1]と照応)、管理者や文化圏に対する慎重な姿勢が窺える。また、名古屋あたりに長門本転写のヒントがあると考えた村上光徳氏の見込みを裏付ける資料が2023年に見つかったこと([10]が該当)、今日までの新しい伝本調査結果([6]が該当)を公表しておくことを、本書刊行の契機に挙げる。
* * *
本書は[6]の伝本一覧を核に据えつつ、各編が連関しあう構成を取る。編者松尾氏が半世紀前に着手し始まった長門本伝本研究は、科研費を得て精力的に調査を進める大谷氏に代表される伝本研究、多くの伝本資料のデジタル化、他領域の研究との融合によって新たな局面を迎えた。平家物語断簡やいわゆる「長門切」を含めた資料群の地道な研究も、長門本の阿弥陀寺奉納以前の姿、さらに約300年に亘る空白期間の本文流動の解明に繋がると松尾氏が見据えていることも留意したい。地道な基礎的研究が新たな知見を示しつつあること――こうした動きは長門本にとどまらず、平家物語研究全体に波及するだろう。その大きな動きを見せる本書は、まさしく「新研究」というにふさわしい。
川鶴 進一(かわつる・しんいち)
早稲田大学大学院文学研究科日本文学専攻博士後期課程単位取得退学。修士(文学)。
現在、早稲田大学本庄高等学院教諭。
著書・論文に、「『北野天神縁起』の教科書単元教材化について」(出口久徳編『絵画・イメージの回廊』笠間書院、2017年)、「長門本」(項目執筆、大津雄一・日下力・佐伯真一・櫻井陽子編『平家物語大事典』東京書籍、2010年)など。