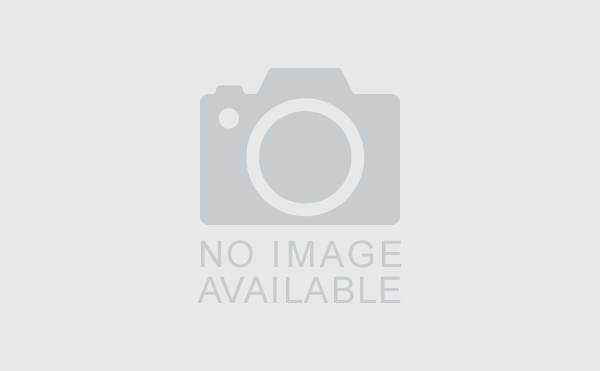学界展望 日本語の歴史的研究 2024年7月〜12月
(北﨑 勇帆)
日本語研究者が「歴史的研究」2024年後期の動向を振り返ります。
【学界展望】
日本語の歴史的研究 2024年7月〜12月
北﨑 勇帆(大阪大学准教授)
2024年7月、小学館『日本国語大辞典』が、2032年の第3版完成を目指して30年ぶりの改訂を行うというニュースがあった*。編集委員は錚々たる面々であり、「改訂の要点」では、「デジタル版での公開」や「段階的にバージョンアップして公開」することも予告されている。内容面もさることながら、特に形式面において、従来の辞書の枠組みを超えた辞書となるようで、今から楽しみでならない。
1.学術誌・論文集
最初に、主要な学術誌・論文集に掲載された論文として、『日本語の研究』誌と、『日本語文法史研究7』(ひつじ書房、11月、以下『文法史7』)*を中心に見ていこう。
まず、『日本語の研究』20巻2号(8月)*には、小原真佳「ゾの係り結びの焦点化機能の変化―中世の語順変更を中心に―」*が掲載された。ゾの係り結びの形骸化・衰退期とされる中世の状況を中心に、ゾの承接語・生起位置・語順変更の有無の変化の3点から、ゾの焦点化機能に変化が生じたという結論を導く。曖昧に用いられがちな「焦点」の概念整理を丁寧に行うことで、従来感覚的に捉えられてきた係り結びの変化の内実が、正確に記述されている。
20巻3号(12月)*には、日本語史に関する論文が3本掲載され、小池俊希「承接順序による係助詞の整理とその機能」は、承接関係の精緻な整理によって係助詞に3種の統語的階層があることを示す。この統語的階層が、係助詞の判断の付与先という意味的差異とも対応するという指摘が、特に興味深い。山中梓「人称詞「こなた」の成立」は、場所代名詞の「こなた」が人称詞化する過程を描く。「近称」の「こなた」が「対称」化するという、一見飛躍的に見える変化は、概略、「区切られた空間・陣営(「こなた」側)にいる(「私」ではない)人」という意味を橋渡しとして成立するという。似たプロセスを経た「あなた」についても次期に刊行されるようで(「人称詞「あなた」の成立」『日本語文法』25(1)、4月)*、こちらも楽しみである。王竣磊「訳官系唐音にみる近世のハ行子音」は、訳官系唐音(長崎の唐通事を起点とする、近世の字音体系)を用いて18世紀のハ行子音の音声実現のバリエーションを推定するもの。そのバリエーションの多さが、近世の脱唇音化が [ɸ>h] のように一気に起こったものではなく、[ɸ~hw] [hw~h] のような中間段階を持つことも示す。資料ごとの性質の異なり(王「訳官系唐音の重層性と原音音系」『訓点語と訓点資料』152、2024年3月*も参照)も踏まえつつ、一つの声母に対し複数の仮名表記が表れるという複雑な状況を見事に整理した論文である。
どの論文も、ある種「王道」とも言えるテーマに別の切り口から取り組むことで新しい知見を生み出す、水準の高い論文である。しかしながら、このように、客観的なデータの提示と記述・理論面での貢献を両立させながら、一方で査読者を十分納得させるためには、現行の紙幅ではかなりの無理をしなければならないように思う。
なお、ハ行子音については『音声研究』28巻2号(8月)*が「音変化における規則性と自然性」を特集とし、高山知明「規則性・自然性から見たハ行音の変化—オノマトペア分裂説の再検証—」*が、「語頭 p 音はオノマトペでは保たれた」(cf. ぴかぴか)とする定説に対し、実際にはオノマトペでも摩擦音化 (p>ɸ) が起こっていたことを論じている。
『文法史7』*所収論文について。青木博史「歴史的観点から見た「青い目をしている」構文」は、「軽動詞構文」というカテゴリで扱われてきた当該構文を歴史的観点からアプローチすることで、自動詞的な「する」の文に由来するものとして、シンプルに説明できることを説く。「する」が「他動詞化」するという見方は Frellesvig, Bjarke「上代日本語の「スル」について—コーパスによる研究」『国語研プロジェクトレビュー』3(3)、2013年3月)*と重なる点があり、言及が欲しかった。
村山実和子「形容詞語幹動詞の自他対応関係の歴史」は、形容詞と関係を持つ自他動詞対において、近代に至ると「高める・高まる」のような型が優勢になり、これらの語の形成が、自動詞化・他動詞化のような一方的な派生ではなく、「―まる・める」を構成要素とする他の動詞からの類推によって成ることを示す。これらの語群が近代にまとまって現れることの理由付けを知りたく思う。
古川大悟「古代語「む」の連体用法の意味について」は、「む」の連体用法を「非現実」「設想」として一般化する従来説に対し、「意志」の意を基本に置いたうえで、「可能性の提起」を媒介に「未来」「推量」の意へ派生するという関係を想定する。連体修飾だけでなく逆接条件にも「意志」らしい例が見受けられること(「ただ今日も君には逢はめど」万葉集2923、古川「助動詞ムの意味—意志から推量へ」『国語国文』92 (2)、2023年2月*も参照)、現代語ではこれが不可能であることを踏まえると、この「意志」が現代語で言う「意志」と同質のものか、規定が欲しい。
林淳子「近世・近代におけるノ有り疑問文使用の拡大」は、「~の?」による疑問文が、「受け入れがたさの表明」など、その場で了解された内容に対する反応から発達することを示す。発話者の心情的側面を意味記述に組み込むのは、現代語での精緻な記述を先に行っていなければなかなか生まれにくい発想であり、その点も含めて面白く読んだ。
矢島正浩「ナラバとナリトモの消長に見る仮定節史」は、近世におけるナラバ節の現代語的用法の整備と、(ナラバと形態的に対応するはずの)ナリトモ節の衰退について、著者が近年主張する「「事態描写」優位から「表現者把握」優位へ」という表現法の変化から説明を試みる。著者自身も「実証が困難」なものと述べるが、(例えば、「文法化」が要因でなく傾向であるのと同様に)これを言語変化の要因とみなすと、議論の循環を招く恐れもある。とすると、種々の形式が「表現者把握」優位の方法に移行していくのはなぜか、ということが問題となろうか。
竹内史郎「名詞の脱範疇化についての一考察—ホドにおける副助詞への文法化—」は「ほど」の副助詞化を題材として、「名詞の副助詞化」という形態統語的変化の記述の方法を提示するもの。「連体節がおさまる従属部のスロットに名詞が代入される」(V ホドノ N → N ホドノ N)というプロセスは、名詞句と準体句との互換性を考えるうえでも興味深い。
このほか、Buckeye East Asian Linguistics Vol. 8(8月)* は、2023年7月に逝去した Charles J. Quinn Jr. の追悼号で、 “Izenkei in Early Japanese Kakari-musubi Clefts: A Provisional Account” は氏の遺稿である。コソの係り結びの成立説は、「コソ挿入説」が定説であるが、これに対し、「焦点句「…コソ」に前提句「…已然形」が後置された2文構造」から成ることを主張する。
Russian Journal of Linguistics Vol. 28(4)(12月)*は、アジア諸言語の「談話標識化」についての特集で、中国語の「原來」と日本語の「元来」の談話標識化の過程を対照する Park, Jiyeon “The Evolution of Pragmatic Marker zenzen in Japanese: From Objectivity to Intersubjectivity” などが収められる。
2.情報学的手法との融合
コーパスの使用は、「コーパスならでは」をどのように実現するかということが依然として課題ではなるものの、調査の手法としては既に標準的なものになったと言ってよいだろう。『武蔵野文学』72号(12月)では、特集「テキストデータのこれから—歴史と未来をつつみこむ TEI」が組まれるなど、分野内外でのデータの共有についても継続的な発信が行われている。
こうした中で、情報学的手法を導入した研究についても、初心者向け教材やプログラミング環境の充実、生成AIの急速な発展に伴って、いわゆる「人文系」を出自とする研究者でもその垣根を越えやすい環境が整ってきている。
例えば、日本語を対象とした研究ではないが、大谷直輝・永田亮・高村大也・川崎義史「深層学習を用いた構文文法の実証的な研究の可能性を探る—better off 構文を例にして—」(『言語研究』166、7月)*は、従来的な人手分類によって得られた仮説を、例文から得られたベクトルのクラスタリングによって検証している。言語学と自然言語処理の研究者が手を取り合った研究であり、ひとつのモデルケースである。稿者も、北﨑勇帆「平家物語の対照コーパスを通して見る中世日本語」(『計量国語学』34(7)、12月)*において、単語ベクトルを利用して、『平家物語』『天草版平家物語』の自動対応付けを行い、そのデータから読み取れることを論じた。相田太一ほか「単語ベクトルの結合学習を用いた近現代語の意味変化の分析」(『じんもんこん2021論文集』、2021年12月)*、近藤泰弘「和歌集の歌風の言語的差異の記述—大規模言語モデルによる分析—(『日本語の研究』19(3)、2023年12月)*、高橋雄太ほか「単語分散表現による日本語和語動詞の書き分けの研究」(『デジタル・ヒューマニティーズ』4(1)、2025年2月)*など、言語変化の分析とベクトルの使用は相性が良く、また、比較的、個人での検証も行いやすいという利点がある。
戸塚史織「役者評判記の形態素解析における現状と課題—評判記を用いた歌舞伎用形態素解析辞書の構築を目指して—」(『論究日本文学』121、12月)*は、国語研による近世語 Unidic が、訳者評判記の解析にどれだけ耐え得るかを検証したもの。「江戸」刊行の評判記であっても、「江戸口語 Unidic」より「上方口語 Unidic」の方が精度が良いようで、これは、純粋な東西差というより、評判記が近世前期の言語体系に近いことを示すものであろう。
このほか、画像処理に関わるものとしては、古典籍への OCR を CPU 環境で可能とする「NDL 古典籍 OCR-Lite」*が11月に公開された(青池亨「CPU 環境で高速に動作する軽量 OCR「NDL 古典籍 OCR-Lite」の開発」(『じんもんこん2024論文集』、11月)*)。デスクトップアプリケーションも公開され、いよいよ「誰でも触れる」ようになったので、是非一度、試していただきたい。
3.「中央の話し言葉」以外の文体・ジャンルへの注目
日本語史(特に文法史)の研究は、記述のレベルで言えば「政治的中心地のくだけた話し言葉」の記述はある程度済んだ段階にあるといってよく、「それ以外」のジャンル・文体・地理的変異に注目が集まっているのは、過去の「展望」でも度々言及されている通りである。
古代語では、訓点資料の文法現象を扱う、辻本桜介「訓点語の「…とならば」「…となり」「…とぞ」について」(『人文論究』74(2)、12月)*、柳原恵津子「『金光明最勝王経』平安初期点における不読字処理の特徴」(『訓点語と訓点資料』153、9月)*があった。和化漢文については、山本久の一連の研究が目立ち、この短期間で「和化漢文における借字表記語彙の展開—古文書の「穴賢(アナカシコ)」を例に—」(『訓点語と訓点資料』153、9月)*、「和化漢文における借字表記語彙の展開—古文書の「度(タシ)」を例に―」(『国語と国文学』101(10)、10月)*、「古文書の複合動詞「―入」」(『国語国文』93(11)、11月)*の3編を、月刊ペースで発表している。「度」は口頭語の「たし」の用法変化を反映し、「…入」は、「恐れ入る」のような謝罪・自己卑下などの対人配慮に多用されるなど、様々なカテゴリについての指摘があり、ともすれば「口語に比して変化に乏しい」と捉えられがちな和化漢文の口語性を問い直す論考群でもある。和化漢文には、「うえは」の機能を「上」の累加の意味(cf. 「うえに」)に求めず、「上」+「者」(確定条件)という語構成から説明する、永澤済「中世和化漢文「上者(ウヘハ)」の機能—「鎌倉幕府裁許状」からみる—」(『文法史7』)*もあった。
室町時代語では、古田龍啓「副詞「道理で」の成立」(『文法史7』)*が、「近年は言語資料として用いられる機会が乏しい」洞門抄物を用いて、「道理で」が接続詞から副詞へと特化する流れを示し、辞書類の初例や既存のコーパスのみでは言語史記述が不十分になり得ることを改めて教えられる。また、資料が「典型的な口語資料」であること自体を問い直すものとして、衣畑智秀「天草版平家物語の疑問詞疑問文—翻訳、文体、歴史の交渉—」(『国語と国文学』101(10)、10月)*が、『天草版平家』に現れる疑問文に、原拠本からの翻訳の干渉があることを指摘する。このほか、山本佐和子「「乾鮭色」の語史—狂言から生まれた言葉—」(『同志社国文学』101、12月)は、「乾鮭色」が「鮭とば」の色から「サーモンピンク」になる過程を文化史的な記述に踏み込んで描くもので、読み応えがある。
近世語では、上方語・大阪語に特徴的な「卑罵語」に注目するものに、西谷龍二「卑罵語の変化に見られる共通性について—複合動詞後項に位置する卑罵語の動作主の有生性に注目して—」(『語文』123、12月)*、村中淑子『「ののしり」の助動詞でなにが表現されるのか—関西方言話者の表現の特質を求めて—』(ひつじ書房、12月)*があった。西谷論文は「形式の「卑語化」当初は有情物主語しか取らず、その後、非情物主語も取るようになる」(その逆はない)ことを論じるもので、「周縁的」と思われている現象も、集めれば見えてくるものがあることをよく示している。このほか、原優花「近松時代浄瑠璃に見られる「古典的」なことばの運用—『国姓爺合戦』の下二段活用動詞の下一段化を中心に—」(『尾道市立大学日本文学論叢』20、12月)*のように、時代物の言語を再検討するものもある。「文語的」「古典的」などというときの「文語」「古典」が何を指すのかということは改めて問われてよいように思うし、この問題については、捷解新語の「規範」を論じた 조강희(趙堈熙)「『捷解新語』における「ゑい」と「よい」両形の違いについて」(『일어일문학[日語日文學]』103、8月)*も参考になる。
近代語では、西川裕香「近代の欧文訓読における too…to 構文の訳と日本語への影響」(『高知大国文』55、12月)*が、英語独習資料の悉皆的な通時調査によって、This coffee is too hot for me to drink. (このコーヒーは熱すぎて私には飲めない)のような too…to 構文の訳が「熟れていく」過程を示し、「基準を満たさない」という新たなタイプの(不)可能構文が、言語接触によって日本語に定着した可能性を論じている。
方言史では、齋藤香織「高知市方言における準体句と準体助詞ガの通時的変遷(2)」(『高知大国文』55、12月)*が、高知方言史資料(武市瑞山書簡など)を用いて、高知市方言の準体助詞「が」が、「のだ」相当の形式へと展開していく過程を示す。このほか、新資料の紹介として、久保薗愛「方言文献としての『藥師瑠璃光如來本願功徳經 直読訓點 完』(一)—紹介と翻刻—」(『岡山大学文学部紀要』77、12月)*や、落語資料の資料性を検討する、安井寿枝「上方古典落語における方言の形式化—速記本『上方はなし』と音声落語の比較を例に—」(『方言の研究』10、7月)*もあった。
なお、ここに「古代語」「近代語」などとしたが、こうした、議論の(便宜上の)前提となる時代区分については、Majtczak, Tomasz “Old, Middle and New: The Problem of Language Periodisation in Diachronic Research on Japanese”(Rocznik Orientalistyczny 77(2), 12月)*による批判的検討があった。政治史的区分に基づかずに言語的証拠のみを用いれば、最も差が大きいはずの「中世前期」と「中世後期」を、同じ「中世」に区分する必要はないということが指摘されており、従来の概説書・研究書が提示する時代区分のレビューとしても一読の価値がある。
4.その他、目に入ったもの
紙幅の制限はないものの、既に規程の文字数は超過している。前節までに触れられなかった研究について、簡単に言及しておく。
4.1 進行中の変化
「進行中の変化」は「歴史」の展望では扱われにくいが、日本語史研究者が常に意識しておくべきテーマのひとつであると思うので、触れておく。
新野直哉「現代日本語の「誤用」定番事例 “気がおけない” の再検討」(『計量国語学』34(7)、12月)*、「最高かよ……」のような「かよ」の用法について、冨永芽衣「複合終助詞「かよ」の新用法— X(旧Twitter)上の使用に注目して—」(『国文(お茶の水女子大学)』140、7月)、谷口悠「和語動詞が前接する「化」の使用動態について—新語「見える化」を中心に—」(『言語資源ワークショップ2024』、8月)*、「超過」を表さない「可愛すぎる」のような「すぎる」の用法について、原田息吹「複合動詞「–スギル」に関する通時的考察—新規用例から見る “過剰” 用法の変化—」(『清心語文』26、12月)があった。特に、落合哉人「個人的な緊急事態— X (Twitter) における「待って」の分析—」(『言語資源ワークショップ2024』、8月)*はSNSの言語を研究する際の方法論の紹介も兼ねており、学ぶところが大きい。
このほか、平塚雄亮「方言の言語変化と維持—福岡市方言の終助詞タイを例に—」(『方言の研究』10、7月)*、佐藤里珠「宮城県におけるガ行鼻濁音の実態—出現環境と意識を中心に—」(『日本文学ノート』59、7月)、山岸和花「長野市における方言使用の衰退について」(『言語の研究』14、8月)など、方言における「進行中の変化」もまた、「日本語史」の範疇である。
4.2 資料・学史など
ワークショップ「キリシタン新出資料・トゥールーズ断簡—日葡辞書稿本とキリシタン版国字本を中心に—」(8月6日、大阪大学)*は、トゥールーズ図書館所蔵本の反古紙に、従来知られなかった『日葡辞書』稿本やキリシタン版国字本などが含まれることの報告で、刺激的であった。次期にまたがるが、報告が、「キリシタン新出資料・トゥールーズ断簡—日葡辞書稿本とキリシタン版国字本を中心に—」岸本恵実・中野遙・白井純・豊島正之『大阪大学大学院人文学研究科紀要』2(2025年2月)*として論文化されている。
肥爪周二「江戸の語学マニアネットワーク—悉曇学者行智を中心に—」(『信州大学人文科学論集』12、9月)*は、蘭学・韻鏡学・国学・悉曇学間の学術ネットワークを探索するもので、これぞ資料博捜の醍醐味といった感がある。悉曇学については、蛭沼芽衣「悉曇学と「清」「濁」」(『西日本国語国文学』11、8月)*もあった。
「現代」の研究者も学史の射程にあり、遠藤織枝『寿岳章子 女とことばと憲法と』(かもがわ出版、9月)*は、新出日記から当時の学術界の雰囲気・風潮や、寿岳の人柄を伝える。小柳智一「【文法史の名著】川端善明著『活用の研究』」(『文法史7』)*は、川端の難解な「活用」論の解説で有り難い。『国語と国文学』101(11)(11月)*は、創刊百周年記念で「国語・国文学研究の百年」を特集する。井島正博「『国語と国文学』に見る文法研究の百年史」、肥爪周二「音韻史研究と『国語と国文学』」など、「『国語と国文学』誌とともに振り返る」側面が強いが、これも一つの学史の編み方であろう。小西いずみ「東條操の「方言」と「方言学」」が説く、東條の意図する「方言」の用語法(=〈ある地域の言語体系〉)には、改めて、自覚的でなければならないと思わされる。
歴史学の方法論の概説書、松沢裕作『歴史学はこう考える』(筑摩書房、9月)*に、「(歴史家は)史料を読み、「とにかくここはこう書いてある」を確認しながら、その一連の作業のなかで、「どこまでは言えるか」を見極めて、読者が納得できるであろう水準と思ったところを文章として提示する」(p.104)とあって、その態度に共感を覚えた。我々の仕事も、資料・データと向き合い、そこから読み取れることを説明することの積み重ねであり、その「どこまでは言えるか」の説得性の担保のため、あるいは知的好奇心の満足のために、本稿が読者にとって何かしらの助けになれば幸いである。
(なお、本稿執筆に際しての文献収集には、西谷龍二氏(大阪大学)の助力を得た。ここに記して感謝申し上げる。)
北﨑勇帆(きたざき・ゆうほ)……論文に、「「不定語疑問文の主題化」の歴史」(『日本語文法』23巻2号)*、「意味変化の方向性と統語変化の連関」(『日本語と近隣言語における文法化』ひつじ書房)*、「原因・理由と話者の判断」(『日本語文法史研究6』ひつじ書房)*ほか。
学会展望 日本語の歴史的研究
バックナンバー