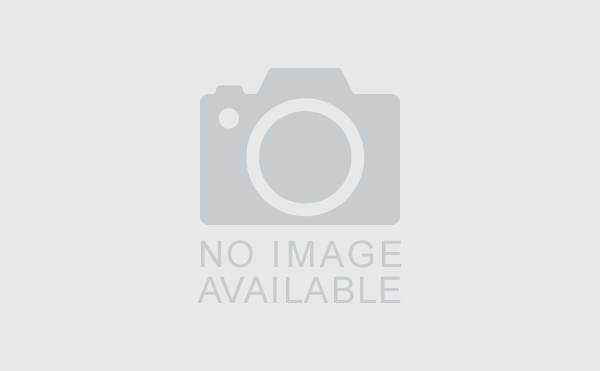シーズン2 第4回
「文学」を考える(前編)
尾山 慎

シーズン2がスタートしました!
「文学」を定義してみる
「文学」とは何だろうか。この問いは、いかようにも答えがありそうだ。たとえば「感動を与えるもの」「高尚な言語表現」「言語による芸術表現」——などなど。が、これらの定義(のようなもの)は多く、主観的な判断に依存しやすい。もちろん主観的でいい場合もあるが、ときに、そこに権威的な意味を帯びる場合があることは注意したい。たとえば上にあえて挙げた「高尚な言語表現」というのは、まずは主観的であると同時に、こういう定義自体が権威を纏う。それはつまり、高尚かそうでないかという上下あるいは高低に分ける線引きをするからで、そこに価値の差が前提される。同じことばや文字で綴られているものに、高低の価値をつけるというのは本当に可能なのだろうか?権威がかかわるというのは、客観的といえるのだろうか?
また別の観点からすれば、高尚かそうでないかという定義は、「文学」が「文学」の範疇を自ずから限定してしまうということにもなっている。あからさまな例でいえば、「「純文学」でなければ「文学」にあらず」(その前に純文学って何だ?というところだが)とか、あるいは「有名作家によって書かれたものでなければ文学とはいえない」などという類いはどうだろう。この線で「文学」をとらえようとおもっても、なかなかこれぞという答えはみえてこないようにおもう。
そこで、今回試みに、「文学」を「さまざまな解釈を許す言語表現」と定義してみよう。ある文章ないし、一文から、いろいろなことを引き出す(引き出しうる)——それは人によって解釈に差がでるということでもいいし、さまざまに寓意を読み取るということであってもいい。この定義によるならば、いろいろな利点があるということを述べようとおもう。それにしても「さまざまな解釈を許す文章」なんて世の中で山のようにありそうだから、となると「世の中の言語表現すべてが「文学」になってしまうのではないか」という懸念があるかもしれない。しかし、実はそれこそが狙いでもある。すべてが文学なのではない。すべてが“「文学」になりうる”のである。つまり、読み手の解釈が起動したとき、それが、他者と違う「個」であるとき、そこに「文学」が生まれているという仮説である。
レシピが「文学」になるとき
上述のように「文学」を「さまざまな解釈を許すもの」と定義するなら、対概念は「解釈が揺れないことば」ということだ。たとえば、マニュアル、レシピ、法令、解剖図、設計図、交通標識、プログラムコードなどがそれにあたる。これらは一義的であること(解釈がぶれない、あるいはぶれないこと)が至上の価値とされ、読み手によって意味が変化しては困る。例を挙げよう。一義的なほうをあえて「非文学」と呼んでおく(後から述べるが前提やら文脈やらによっては「文学」になってしまったりもするのだが)。
「塩を小さじ2杯加える」(料理レシピ/非文学)
これに対し、「塩を小さじ2杯、ため息と一緒に加える」はどうだろうか。これは「文学」だと筆者は考える。「ため息と一緒に」がどういう解釈を呼ぶか。ことばに余白と詩性を生み出し、解釈の一義的固定から解放する。「胡椒:少々」は非文学であっても、「胡椒:気が済むまで、情熱的に」は「文学」だ。このように「文学」という概念を柔らかく自由度を高く設定してみよう。このとき重要なのは、「文学」と「非文学」は本質的に断絶しているのではなく、連続的なグラデーション上にあるとみるということだ。レシートの明細も、日記の一節も、読み手がそれに物語や感情を読み込むことで「文学」へと変わりうる。この柔軟性をして「解釈の現象としての「文学」」と仮説をたてたわけである。
AI が生成する文章は文学か
日記、エッセイ、広告コピー、コラムなどは、いま上にみた定義でいうところの「非文学」と「文学」の中間地帯に存在することがよくある。これらは本来は、情報伝達や私的記録の目的で書かれるが(つまり「非文学」寄り)、ときに「文学」的効果を帯びる。たとえば美容系の広告で、「しわは時間のせいじゃない。生きてきた証だから」などとあったとすれば、商品の宣伝にそえられた詩の一節のようなもので、CM のパッケージ全体としては非文学よりであっても、そえられたことばはこうして「文学」を内包することがありうる。
従って、作者の意図にかかわらず、読み手が読み手の解釈として読み、それが他の読み手と比して一義的でないなら、そこに「文学」は成立する。解釈の数だけなどというと、茫漠と、あらゆる文章が該当してしまわないか——そのとおりだ。が、このとらえ方の利点は、純文学だとか、有名作家の名前に依存しない、「読み」に基づいた評価軸を提示することができるというところにある。
生成 AI の進歩がめざましいが、たとえば AI が生成した文章は「文学」ではない、という主張はどうだろう。筆者は近時、もしそう断じられるとしたらその根拠は何だろうと考えてきた。たとえば「意図がない」「魂がない」「熱意がない」などという理由だろうか?たしかに AI には情熱や信念はないので、ひたすら膨大な無数の演算の結果といえばそれまでだ。しかし、それがそのまま「文学」とはいえないという帰結に導かれるためには、「文学とは情熱と信念による産物」という定義が先に了解されている必要がある。が、これは極めて主観的かつ、検証不能なことではないか。
そこで、「「文学」とは読みの可能性である」という定義を採れば、意図や魂の有無、情熱の度合いなどというのは問題ではなくなる。AI が生成した文章であっても、ある読者が涙し、共感し、思索をはじめたその時点で、その文は「文学」であるといっていいとおもう。「読むこと」が「文学」の起動装置とみれば、人間によるか AI によるかは副次的要素にすぎないことになる。この見方をすることで、有名な作家が書いたから、高名な賞の受賞作品だからといったような、権威による「文学」の定位という方法からも距離を置くことができる。筆者は、AI の生成物にもそうして文学的価値を見出すことは、人間の感受性と創造力を肯定するものであり、むしろ今後の「文学」に新しい地平を開くのではないかとおもっている。
設計図に「壁厚150 mm」とあるとする(「非文学」)。しかし、その説明で、設計士が「寒さと孤独に、ちょっとだけ強くなれる厚み」などとそえたなら、それは設計でありつつ、同時に詩でもある。こうした小さな瞬間においても、「文学」とは、ジャンルや制度による限定を、あっさりと、軽やかに越境してくるものだとおもう。
非言語的文学──絵画や音楽も
ことばによらない表現、たとえば絵画や音楽においても、読みの可能性が開かれている場合、それは「文学」であると見なせる。ミレーの『落穂拾い』がキリスト教的美徳とも貧困の象徴とも読まれるように、「解釈の多義性」がそこにある。それはまさに「文学」だ。
このように、読みの可能性、解釈の幅を許すものを文学としてみる、読まれることによって文学になるといった仮説的発想を制度的に応用することで、教育・出版・AI 倫理の各領域において新たな展開が期待できるのではないだろうか。
教育においても、「正しい読み方」というより、読解が生まれる過程そのものに価値を置く授業なるものも、将来的には期待したい。たとえば、AI による生成詩や無名の文章を素材に、生徒がそれを「文学として読む」演習は、読解行為の創造性を実感させるかもしれない(一部は実践されてはいるだろう。そしてもちろん、児童・生徒の学力によっても差がでるだろうし、なにより指導する先生は大変かもしれないが)。「AI 創作は無意味」とする前提を見直し、「意味は、読む人間が見出していく」という認識に基づいた評価の枠組みがあらためてできてくる。人間ではない AI が生成するものへの「文学」的評価をそうして認めることは、逆説的に、人間読者の感受性や解釈能力が中心的価値となることを導くのではないだろうか。
従来の「誰が書いたか」「どのジャンルか」といった評価基準に代わり、「どう読まれた(る)か」「多義的な解釈が生まれた(る)か」を重視するのは、かなり、おもしろいのではないだろうか。どれほど解釈の可能性が開放されているかということ、それ自体を考える。やや大げさな言いだけれど、多くの読者の参加による開かれた解釈が可能な、そんな「文学」の民主化が促進されるとおもうのだ。
著者紹介
尾山 慎(おやま しん)
奈良女子大学教授。真言宗御室派寳珠院住職。
著作に『二合仮名の研究』(和泉書院、2019)、『上代日本語表記論の構想』(花鳥社、2021)、『日本語の文字と表記 学びとその方法』(花鳥社、2022)。
次回は7月25日頃の予定です。