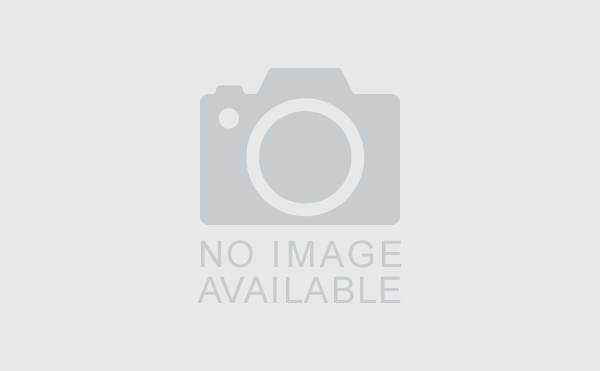シーズン2 第10回
学術研究という「総合病院」
尾山 慎

コラム延長戦!「文字の窓 ことばの景色」。
病院の「科」と身体の一体性
大きな病院に足を踏み入れると、そこには多くの診療科が並んでいる。内科、外科、小児科、産婦人科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、整形外科、精神科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科……など、大病院であるほどに、かなりの数が並ぶ。さらに内科だけでも、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、腎臓内科、神経内科といった具合に細分化されている。しかし、私たち自身の身体に、本来そのような境界線が存在するわけではない。仮に、胸や腹を開ける手術をしても、「ここから先は循環器内科の管轄です」「ここまでは消化器内科の領域です」などと書かれているわけでもないし、仕切りが立っているわけでもない。心臓(循環器)と肺(呼吸器)は膜一枚で隣り合い、血液は全身をめぐり、神経は体の隅々まで張り巡らされている。呼吸も循環も消化も代謝も、ひとつの生命のリズムとして一体になって働いているわけである。
この「一体性」とは、特段、解剖学的な知識を持ち出さずとも、日常生活の中で実感できることである。食事をすれば消化が進み、血糖値が上がり、頭の働きが活発になる。試験前に緊張すれば心臓が高鳴り、手のひらに汗がにじむ。徹夜をすれば胃腸が重くなり、肌が荒れ、思考力が鈍る。これらの経験は誰もが持っている。つまり、私たちは普段から「身体は部分ごとに分かれているのではなく、本来一体である」ことを、自分の感覚で知っているだろう。それにもかかわらず、医療の現場では便宜上、分けざるをえない。あまりに複雑な〈一体として稼働するすべて〉をひと括りにして、一人の医師が同時に一手に担うのは不可能だから、そこで専門分野を設け、臓器や働きごとに担当、研究を分担している。上に挙げたような診療科の区分は、人体があらかじめ細かく分かれているから存在するのではなく、本来一体のものをあとから分割しているわけである。そして、その分割とは、つまりは人間にとって「発見」でもあった。「分かる(分かった)」から「分けられる」のである。
学問もまた、これに同じである。本来の、学問の対象とは自然であれ、人文であれ、切れ目なく連続し、一体のものとして存在している。現状、最大限に広く括れば、研究領域として自然科学/人文科学といった大分類があるが、これとて本来一体であるだろう。人間という存在の情動、活動は、動物の一種としてこの自然のなかにあってのもの・ことだといえるからだ。それをそのまま包括的に一体のままに扱うことは難しいからこそ、分化に分化を重ねて、言語研究で言えば「音韻」「文法」「意味」といった分野に切り分けて研究を進めてきたのである。
どれも大事で、優劣はない
たとえば、心臓と脳と血液のどれが一番大事か?と問うてみよう。この問いがナンセンスであることはすぐにわかるだろう。心臓がなければ血液は流れない。しかし、血液がなければ酸素や栄養は運ばれない(心臓や脳は動かない)。そして脳がなければそもそも身体全体の調整はできない。つまり、いずれが欠けても生命は成立しないから、どれが一番、ということはない。人体はこのような相互依存のネットワークとして機能している。神経が血圧を調整し、腎臓が体液のバランスを保ち、内分泌がホルモンを放出して全身の働きを調整している。免疫系は外敵を防ぎ、呼吸器は酸素を取り込み、消化器は栄養を吸収する。すべてが相互に作用し合い、全体がかみ合い、つながり、調和しつつ、「生きている」のである。というわけで「どれが一番大事か」という問い自体がおかしいわけである。そしてこれになぞらえれば、言語研究において音韻論、文法論、意味論など、それぞれが独自に重要ではあるが、互いに関係し、依存し合ってもいるということであり、「音韻こそ根源だ」「意味こそ本質だ」といった単純な優劣づけは、学問の全体性を見誤らせることにもなりかねない。
専門家の存在の必然
便宜的な切り分けだからといって、専門性が不要になるわけではもちろん、ない。心臓の手術は循環器外科医でなければ行えず、胃癌の切除には消化器外科医、脳出血の処置には脳神経外科医が必要である。専門家の存在は臨床に不可欠である。しかも専門家の知識は単なる「部分」の知識ではない。循環器内科医は心臓と血管を深く研究するが、その知識は腎臓や内分泌の働きとも結びついている。たとえば腎臓の不調が高血圧を招き、ホルモンの異常が心臓に負担をかける。専門性は、全体から切り離されて存在するのではなく、むしろ全体を理解するための窓口のようなものだ。やはり、言語の研究も同じで、音韻論は文法や意味論との連関を抜きにしては結局のところ理解できない。専門家は分担の枠内で活動しながら、全体との接続を意識し続けているのであるし、またそうでなくてはならない。
言語研究へのなぞらえ
ここであらためて、言語研究の領域を「病院」にたとえてみることにしよう。音声学はやはり発音器官や聴覚を扱う耳鼻咽喉科に引き当てられるだろうか。文法論はしくみとか構造を考えるから、身体の骨格や筋肉を扱う整形外科にたとえるのはどうだろう。意味論は精神や神経に関わる神経内科に見立ててみようか。そして社会言語学領域は、生活習慣や環境と結びつく公衆衛生学に対応するかもしれない——と、もちろんこれは試みのたとえにすぎない、他愛ないものだ。しかし、どの科も一人の患者の健康に不可欠であり、かつ連関しあうのと同じように、どの分野も言語という全体を理解するうえで欠かすことはできない、ということが知られるはずだ。
筆者は文字・表記論が専門であるが、以前、ある先生とお話したとき、筆者の研究について、「表記論をやるということは、皮膚科医のようなものだよ」といわれたことがあった。この比喩はきわめて示唆的で、ずっと大切にしていることばだ。皮膚は人体の最も外側にあり、誰の目にも見える。湿疹、発疹、かゆみ、しみなど、症状が、この表面に様々に現れる。だが皮膚科医が診ているのは単なる皮膚の表面だけではない。皮膚症状の原因は全身に求められるのだ。アトピー性皮膚炎は免疫系の過敏反応と関わり、真菌感染は微生物学の知識を要する。黄疸は肝臓疾患が皮膚の色に現れる例であり、糖尿病は皮膚潰瘍を招きやすい。精神的ストレスが蕁麻疹を引き起こすこともある。皮膚にあらわれる疾患は、全身のなんらかの不調の鑑のようなものであり、皮膚科医はその表面を入口にして、全身を読むことが求められる。
たしかに表記論もこれにとてもよく似ている。文字は、物理的に刻まれる記号であるがゆえに、言語の「表面」に、目に見える形で現れる。字体、仮名遣い、異体字、清濁の表記など、見えるという点では、非常に明らかな存在である。しかしその背後には音韻体系や文法、語彙、社会的規範、歴史的条件が複雑に絡み合って存在している。それが単なる文字の物理的な形や点画の違いだけではなく、音韻構造や漢字音、社会的・文化的条件が交錯していることによるケースもある。表記は言語の、目に見える表面現象でありながら、言語全体を映し出す窓であるともいえるのである。表記論の研究者は皮膚科医と同じように、表面に現れる現象を手がかりに、その背後にある全体の仕組みを読み解く必要がある。これからも文字だけ眺めているのではダメで、音韻も、文法も、語彙も全部、たゆまず深く学び続けなければならないと、その先生のことばのおかげで、思いを新たにしたものだった。
本来一体の学問と医哲同源
以上見てきたように、学問とはさながら総合病院のごとしであるが、繰り返すように、各分野は決してア・プリオリ(=もともと、事前に、所与として)に分かれていたわけではない。心臓を研究するときに脳や血液を「関係ない」と切り離しているのではなく、便宜上いったん横に置いているだけのことだ。現実には互いに密接に関わっており、全体を無視しては成り立たない。音韻、文法、意味、語彙、表記といった区分をするが、本質的には言語はひとつの有機体であり、どの側面も全体に連なる。
古代ギリシアの学問は、まさにこの「切れ目のなさ」を前提としていた。ある意味茫漠たる連続の上に打ち立てられるものであった。ヒポクラテス派の医師たちは、病を神話や呪術ではなく自然の摂理で説明しようとした。その営みは医学と哲学が未分化であったことを物語っている。医と哲は同根であり、身体の仕組みを理解することと、自然や倫理、人間の情動、この世界の仕組み、論理を理解することとは切り離されていなかった。アリストテレスにおいても、自然学、倫理学、政治学、形而上学は一つの知を異なる角度から照らしたにすぎなかった。
現代の学問が細かく分かれているのは歴史的に生じた分化の結果である。前述のように、それはたしかに進歩的な、人間知性の革新による成果だ。事実、そういった方法として区分をもうけたことで、専門性が育ち、知の深化が可能になった。しかし同時に、全体を見失わない態度がますます不可欠となる。今日よくいう学際的研究とか、異分野協働とか、あるいはまた文理融合などは、必然的な反省であると同時に、新規な試みなのでは全くなく、むしろ学問の本来への回帰に近いといえるだろう。
学問とは、本来その対象が切れ目なく一体でありながら、研究するに当たっては便宜上分けられ、専門家によって掘り下げられる――というふうに成り立っている。「自分の体は本来ひとつである」という実感は、素朴にギリシア以来の「医哲同源」の思想に列なるが、人類の学問が幾星霜を経て細分化に細分化を極めて至った、この現代の学問探究においてこそ、むしろ、常にそれは思い起こされねばならない。学究を進めることとは、切り分けられて閉じられた分野に安住せず(蛸壺に引きこもらず)、全体を見据えながら専門を掘るという両輪的営みである。そしてそれをまた次代へとつないでいくことなのである。
著者紹介
尾山 慎(おやま しん)
奈良女子大学教授。真言宗御室派寳珠院住職。
著作に『二合仮名の研究』(和泉書院、2019)、『上代日本語表記論の構想』(花鳥社、2021)、『日本語の文字と表記 学びとその方法』(花鳥社、2022)。