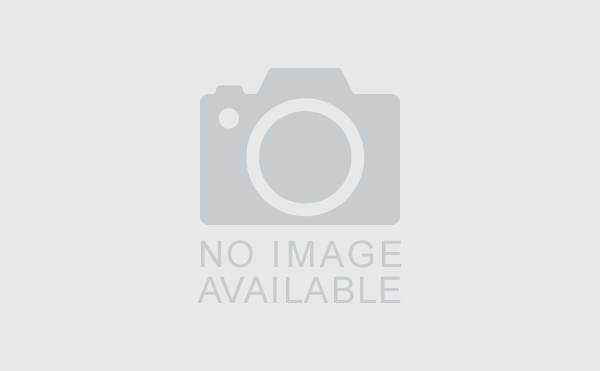シーズン2 第6回
漢字廃止へのまなざし
——文字とことばの「国際化」とは(前編)
尾山 慎

コラム延長戦!「文字の窓 ことばの景色」。
漢字を廃止するというビジョン
日本において、漢字を制限あるいは廃止しようという考えや活動はゆうに150年の歴史をもつ(詳しく学びたい人は安田敏朗『漢字廃止の思想史』(平凡社)を読まれたい)。とはいえ今日、漢字はなくなってはいないし、そもそも日本は、公には少なくとも2025年現在、〈いつか漢字をやめる〉というビジョンはもっていないことになっている。なぜそう断言できるかというと、かつて当用漢字という(〝当面用いる漢字〟という意味、「当用」からそんな意味はとりにくいのだけれど、それはさておき)、〝いつか漢字はやめる〟というビジョンのもとに約1800字の枠組みを作ったのに対し、現在は1981年から続く常用漢字というのを目安にしているからである。まさに常用の「目安」としてリストアップされたものだ(その点、当用漢字は「目安」ではなく「制限」だった)。常用漢字とはその名の通り、社会で標準的に使用する漢字群を指すのだが、「当用」ではなくて「常用」ということは、つまりこれに置き換わった時点で、〈いつか漢字はやめる〉ビジョンではなくなったということなのだ。もちろん、いつか漢字はやめる、やめたほうがいいというような議論を個々にすること自体は、これからも自由であるが。
今回は、この漢字をへらす、やめるということにまつわってよく言われる意見、展望などについて、いろいろ考えてみたいと思う。
「なくなる」と「なくす」は違う
漢字はどんどん減っていって、いつかなくなる(辞書等の書物には残るだろうし、物理的になくなるわけはないから、人々に使用されなくなっていくという意味だろう)と見通す研究がある(野村雅昭『漢字の未来 新版』、三元社)。一方で、漢字はなくすのがよい、とも言われる(野村氏同書など)。しかし、「なくなる(なくなっていく)」のと「なくす」のは区別したほうがいい。「なくす」からこそ「なくなっていく」ということは言えるが、やはり、次第に使われなくなっていく方の減少は、人為的に排除するのとは別の流れであるとみておかなければならない。
なぜここにこだわるかというと、廃止論の論拠の一つに、そもそも漢字の使用は自然に減っていっているという統計的研究があるからだ。いわゆるカタカナ語(外来語)の使用機会が増えるなど、様々な理由から、漢字は未来にわたって徐々に減っていく一方だというのだ。単に感覚的な意見ではなく、実際にデータがある。『図説日本語』(林大監修 宮島達夫・野村雅昭ほか編 角川書店)によれば、1900年から55年間、100人の作家による100編の小説から1000字ずつを抽出して、漢字含有率を調べると、1900年~1905年は393字だったが、1950年~1955年では275字になっているという。この傾向が続くと、理論上は2031年に0になる計算である。が、もちろん漢字が少なくなればなるほど保護する機運が強まり、0になる日は永久に来ないという予測も同時に立てられてはいた(実際、さすがにあと6年で漢字が0になるとは思えない)。しかし、どちらにしても、減る方向にはあれど、増えることはないという見立てである。こういうことをもとに、ほら、漢字ってもう斜陽だから、この流れにあらがって無理に守る必要はない、なくなっていくのがあるべき姿だ、という主張へとつながるわけである。それでも、これは「なくす」のとは違うはずだ。「(自然に)なくなっていく、減っていく」ことと「人為的になくす」こととをごっちゃにしてはいけない。なくすというのは、社会から、ということだから、そうなると多分いくつかの法律があらたに必要になる。ということは教育と政策が必ずセットで動く必要がある(『日本語の文字と表記』第4章Ⅱ参照)。つまりは自然に〝なくなっていく〟のとは社会的な動きが違うものになるはずで、漢字をなくす/なくなる——は、ことばと文字の未来を考えるにあたり、重要な違いなのである。
書き方が複雑多様であることは〝害悪〟か
漢字廃止の論陣をはるときの、大きな論点の一つが日本語表記の多岐にわたる複層的実態である。ふりがなを振れば、かなり無茶な読みも可能で、単線線路を、一部分複線にするかのように、二重の意味を負わせたりできる(たとえば「涙」と書いて「よろこび」と振れば、涙を流しているが、うれし涙というのを同時に表せる。また漫画などで、吹き出しの台詞にはそのキャラクターの名前が書いてあるのに、ふりがなは「おまえ」になっていたりすることがある。ふりがなのほうがむしろ本文(実際発せられたセリフ)で、漢字のほうが解説にまわっているような例。シーズン1 第4回)。

また送り仮名の曖昧さ——焼き肉/焼肉、受付/受け付け——、文字上では一緒なのに別語(十分(「10分」と「じゅうぶん」)、手拭(「てふき」「てぬぐい」))といったケースなど、その複雑さ、多様さは枚挙にいとまがない。こういった、いいように言えば自由さ、悪いように言えば統一性のなさ、複雑さということから、日本語表記は、近代的な国家の言語の様態としてよくないという考えがある。たとえばドイツには正書法があって、しかもその見直しを国家政治主導で幾度も行ってきた例がある。一番最近は2004~2006年で、さかのぼると1901年、ベルリンで「正書法会議(Orthographische Konferenz)」が開催されたという歴史ある取り組みである。日本は文化庁が表記の目安を出しているが、上述の通り、実際は多様で、正書法=オーソグラフィは、ない。野村氏(前掲書)は「なんらかの標準的な表記法が存在しないなどということはかんがえられない。それ(筆者注:標準的な表記法があるということ)が近代国家における言語というもののありかたなのである」として、日本語に正書法が無いことに警鐘を鳴らす。
「斉藤」や「渡辺」に統一すべきか
サイトウさんや、ワタナベさんは、いろんな漢字表記がある。いくつか列挙すると、「斉藤」「斎藤」「齊藤」「齋藤」、「渡辺」「渡邊」「渡邉」など。戸籍上決まっているが、文字化けしたり、人に正しく書いてもらえないことも多いので、公文書以外はもう最初から簡単な漢字でいいことにしている人や、反対に、どんなときでも常に正確に書きたい/打ちたい(名前だから)という人もいるだろう。筆者の知り合いのワタナベさんは、自分では必ず「渡邉」と書き、決して「渡辺」とは書かない。しかし、公的なものをのぞき、人が自分の名前を書く分については「ベ」が「部」になってしまっている以外は、「渡辺」などとあっても基本的に従う(わざわざ訂正はしない)ことにしている、という。なかには自分あてに「渡邊」と書かれたのをみると、〝頑張って書いてくれたのに悪いけどこっちの「邊」じゃないんだよね(正しくは「邉」)〟と思ってしまうが、黙っているとのこと。
ここには、合理性ということと、文化的精神的なものとして漢字表記を守りたいという、大げさに言えば〝せめぎ合い〟がある。自分は守るが人には求めないとか、いろんなレベルで、どこかで折り合いをつけたり、つけなかったり——。そういう意味では常に天秤が揺れているようなものだ。いずれに傾くかは基本的に個人の自由だろうと思う。同じ人がその時々(の気分)で変わっても構わないことだ。が、かように表記の基準、正書法がないということを言語の制度的欠陥ととらえる見方からすれば、この〝カオス〟こそがまさに、容認しがたいことなのかもしれない(個人的には、筆者は現状で別に大筋いいんじゃないか、と思っている立場である)。
社会でもう「斉藤」という簡単な字に限ってしまって、表記はこれだけに統一したらいいいのではないかという意見がある(鈴木孝夫・田中克彦『対論 言語学が輝いていた時代』岩波書店)。つまり、ほかの「齋」「齊」などは排除してしまうのだ。これらの異体字はいわば同字のバリエーションでダブついているものであるから、社会的には無駄と考えるという、かなり鋭利な合理主義的考え方である。サイトウさんは一律「斉藤」とすればよく、当のサイトウさんたちもそれに従う――ということで、筆者は、本書の初読時にこの考えにはちょっと驚いた。いくらなんでも「サイトウ」さん本人を差し置いてこのように社会で決めてしまおうというのは乱暴じゃないかと思ったのだが、文字とは〝社会における共用の具〟という見方に立てば、その社会的合理性という観点でこのような少し極端な見方もあり得るということだろう。議論としては、興味深い。それに、人名という固有名詞なので筆者は引っかかりを覚えたわけだが、一般語なら「もう簡単な表記でいいんじゃないの」と思うことはたくさんある。事実、「交差点」や「汚職」のようにもう学校でそうだと習って、もはやそれが正しいとされるものもある(本来は「交叉点」「瀆職」(トクショク))わけだから、サイトウさんの表記を守れ!などと叫ぶのは、実は視野狭窄で、ある意味滑稽なのかもしれない。また固有名詞でも「タイワン」は、旧来の書き方で言えば「臺灣」というかなり厳つい表記になるが、画数もものすごく多いし、まぁ「台湾」でいいじゃないかと、考えるところはある。合理・功利か、文化・伝統か。制度的な側面と、文化的な側面の両方に、漢字を巡る問題は横たわっているのである。
著者紹介
尾山 慎(おやま しん)
奈良女子大学教授。真言宗御室派寳珠院住職。
著作に『二合仮名の研究』(和泉書院、2019)、『上代日本語表記論の構想』(花鳥社、2021)、『日本語の文字と表記 学びとその方法』(花鳥社、2022)。
あるいは反対に、外国語が日本のカタカナを導入したらどうなるでしょう?
![]() シーズン2 第7回 漢字廃止へのまなざし——文字とことばの「国際化」とは(中編)
シーズン2 第7回 漢字廃止へのまなざし——文字とことばの「国際化」とは(中編)
![]() シーズン2 第5回 「文学」を考える(後編)
シーズン2 第5回 「文学」を考える(後編)