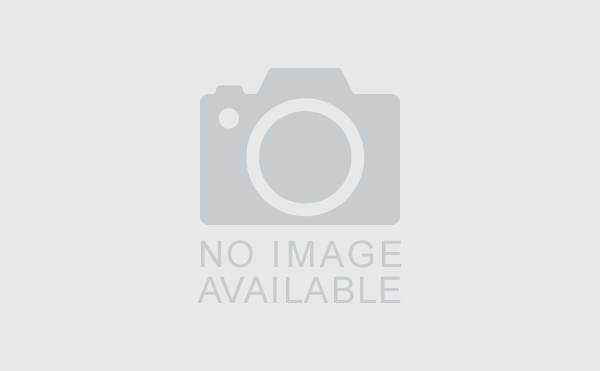シーズン2 第7回
漢字廃止へのまなざし
——文字とことばの「国際化」とは(中編)
尾山 慎

コラム延長戦!「文字の窓 ことばの景色」。
世界共通文字はありえるか
結論から言うと筆者は、世界共通文字というのは、ほぼ無理だろうと思う。無理というか、労のわりに、益がほとんどないと言ったほうがいいかもしれない。世界共通「語」と言えばエスペラントの例があるが、エスペラントとて実態はスペイン語やイタリア語に近く、どう考えても日本人が一から学ぶのは、それらの母語話者に比して不利である(エスペラントは、youtubeで視聴できる。欧米の、とくにロマンス系言語(スペイン語、イタリア語など)の人の書き込みが面白い。「はじめて聞いても、めっちゃわかるんだけど」みたいに言っているスペイン人やイタリア人がいる)。
たとえば、
aqua /ˈa.kʷa/ もとはラテン語:(水)
→ (エスペラント)akvo /ˈak.vo/
buona /ˈbwɔ.na/ イタリア
buena /ˈbwe.na/ スペイン:(良い)
→ (エスペラント)bona/ˈbo.na/ など。
これははっきりいって相当学習のアドバンテージがあると言わざるを得ない。ロマンス言語話者にとっては、エスペラントはこのようにしばしば語彙が「どこか見たこと、聞いたことがある形」で現れる。
現状、世界共通文字の理想に一番近いのは、使用の相対的頻度からいってアルファベットかもしれないが、もとから使っている言語とそうでない言語に、あれこれ差がでてしまうかもしれない。世界共通文字なるものの構想に理念があるとすれば、それは一体感だとか、共通による公平性、相互理解の向上などであるのだろうが、それを掲げるにもかかわらず、最初からもう格差、断絶、誤解(誤読)ありき、というような皮肉なことにもなりかねない。それは世界の誰もが初めて見る共通文字を開発するとしても実は似たようなことになるかもしれないのである。そしてそもそも肝心なことだが、だれが「新規な世界共通文字」を、どうやって、どれだけ時間をかけて作り、どのような方法で普及させるのだろう?
発音は共通化できない
言語の発音は、あたりまえだが、おのおの違うし、これを統一することは不可能なので、必然的に、仮に文字は同じでもそれが〝方言化〟してしまうのは必至である。世界共通のことばや文字の構想で、いつも抜け落ちていると思われるのが、方言化の問題だ。そんなことは方言化が起きてから考えればいい……とはいかない。それはあまりにユートピア的楽観であって、「なんとかなるってー」とか言っているのと一緒だと思う。世界共通文字を作っても、言語にあわせて必ず、時間とともに使用の様態は変わっていく。そうすると、同じなのは個々の文字の見た目だけということにもなるが、ならば文字を共通にするということにそもそもどれほど意味があるのか?というところへ帰ってきてしまうのではないか。同じ形の文字なのに、綴ると読み方が全然違うということにもなっていく。せっかく新規に文字体系を作っても現状とあまり変わらないところへ結局落ち着くかもしれないわけである。
次のカタカナ文字列をみていただきたい。
アー・ムアール・アーダ・ンーバーヤ・ルア・ーフィ・フイサ・ルア・フイサ・ルア ※
ヤーイーアーワーィツィスイ・ルア・クィータナマ・ルア・フバシュヤ・ナッジ・ンルッ
これは試みに、アラビア語をカタカナで書いてみたものである。しかもアラビア語は右から左へ綴るので、ここでもそうなっている。上記で言えば、※から、ア→ル→サ→イ→フと読んでいく。しかし、普通、カタカナで書かれていたら、左から読むにちがいない。つまり、左端から「アー・ムアール……」と読み始めた人がいま、多いのではないだろうか。よって、日本語話者が直感的に読みやすいようにするなら、左から右へと書きなおした「アル・サイフ・フィー・アル・ヤーバーン・ハーダ・ルアーム……(今年の日本はとても暑い。まるで熱帯のようだ)」だろう。いま、カタカナがアラビア語の発音を到底表し切れていないことを度外視して(これを度外視するのは本来おかしいが)、サウジアラビアの人たちはじめアラビア文字圏の人々がこぞってカタカナを導入したとしよう。そのことに、何かいいことがあるかと言われると、まぁ、ないんじゃないだろうか。
そして一番肝心なことだが、アラビア語話者が、カタカナ表記を採用して、しかし、アラビアネイティブ発音でこのカタカナ文字列を読んだとしたらどうだろう?文字表記「アル・サイフ」はもうaru・saihuという発音ではないということだ。私たちはカタカナを日本語として読むゆえに、そのことに、ものすごく惑わされるに違いない。
各言語の別を超えた文字の共通が、ほかのあらゆるネガティブ条件をキャンセルするほどの目覚ましい効果をもつなら別なのだが、どうもそうではなさそうだ。アラビア語表記を例にとったが、日本語の文字と外国語の文字の関係を逆転させても同じことである。
日本語のローマ字はヘボン式のフがfuである以外はハ行音でhを用いるが、フランス語やイタリア語、ポルトガル語などは「h」を書いてもほぼ発音しない。こういう言語の人たちは、日本語の haha(母)や hoho(頬)をちゃんと読んでくれるだろうか。日本語の場合は「h」を日本語の、喉で出す音で読むのだ、と別途記憶しないといけないのなら、現状とあんまり変わらないのではないか。むしろひらがなを覚えて、日本語を読んでもらった方が早いかもしれない。見た目が同じだけにかえって紛らわしいということは、きっとあるはずだ。「文字の世界共通」へと乗り換えるとして、こういった問題は無視していいリスクなのだろうか。
Michael と綴る名前は、欧米で広くある名前で、言語ごとに発音がいろいろ違う。英語ならマイケル、ドイツ語はミヒャエル、フランス語はミカエルないしミッシェルとなる(ちなみに、ロシア語はキリル文字でもう綴りは違うが、もともとは同じ人名で、読みは「ミハイル」)。共通の文字だからこそ読み方が乱立するするということはあり得るのだ。英語の gift は、全く同じ綴りでも、なんとドイツ語では「毒」である(状況によってはとんでもないことになりそうだ)。

「取り扱いは慎重に」
漢字廃止、世界共通の文字を——!と叫ぶなら、文字を共通にすることのリスクやデメリットも、必ずセットで議論されてしかるべきだ。日本語の「と」はローマ字で書くと to だが、:watashi to anata が “私とあなた” ではなく、英語話者は「to」で思わず、AtoBの構文に読んでしまうのではないか。
世界共通文字を構想する議論をするにあたっては、以上のような問題点にも言及し、これらを見渡したうえでの設計であってもらいたい。こういうリスク寄りの話を一切せずに、みんなで共通の文字を使えば便利だしわかり合えるからと空想するだけでは困るのだ。
「やさしい日本語」の意義
災害マップや病院の案内に「やさしい日本語」を用いることは、命を守ることばの選び方である。多言語対応が理想ではあるが、現場の制約や人材の限界から、それが常に実現するとは限らない。そんなとき、外国人にも伝わりやすいシンプルな日本語をあらかじめ設計しておくことは、共に生きる社会を築く第一歩となる。特に災害時や医療の場では、一秒が生死を分ける。そしてそこで使われることばが難解であれば、理解の遅れが致命的となりうる。「逃げてください」「ここは安全です」といった単純で明快な表現、誰にでもわかる形に整える努力は、単なる翻訳以上の価値をもつ。日本語を母語としない人々と、同じ場所で、同じ情報を、同じ重みで共有するために、やさしい日本語は不可欠である。それは「外国人のため」というより「共に生きる社会のため」にこそ必要だと言える。
一方、別の観点からも考える必要がある——やさしい日本語はそうした、緊急時や即時の理解が求められる場面において効果を発揮する言語的工夫であって、すべての状況に万能なわけではない。たとえば長期滞在者や日本への帰化を目指す学習者に対しては、むしろ標準的な日本語に触れ、複雑な構文や語彙にも段階的に慣れていってもらうほうが自然であり、常に簡略化された表現だけを提供することは、時に足枷となりかねない。やさしさとは、常に簡単さを意味するのではない。
日本語の上達自体を目標とする人、日本語母語話者と高度に抽象的な内容を議論、討論したい人、商談、交渉、通訳したい人、専門書の翻訳をしたいひと——学習の上限というのは、本来ない。どこまで突き詰めても良いし、どこまでいってもゴールはないとおもいつづけて取り組むのは、各人の自由である。それらをも毀損、制限してしまうような「やさしさの強要」であってはならないと思う。
漢字廃止論は「やさしさ」なのか
よく、漢字は一生勉強しても終わらない、という。本当にそのとおりだろう。数万字を覚えられる人などまず、いない(使う機会がないという点でも、記憶を保持する理由があまりない)。しかし、〈一生勉強しても終わらない〉ことをネガティブにだけとらえていいものだろうか。漢字廃止を構想するとき、その理由の一つに、母語を書く文字なのに一生勉強しても終わらないと悲観的に語られることがある。が、筆者はこの悲観には必ずしも共感できないところがある。難漢字はそもそも基本的に自由学習に委ねられているというのもあるが、それをいうなら英語も数学も、歴史も、一生勉強したって終わらないものだろう。社会、道徳、倫理にしてもそうだ。確かにアルファベットに比べればはるかに多いし、アルファベットは「全部知っている」と言えるが、漢字はそうではない。が、その、やってもやっても終わらないことが、果たして制度として漢字を廃止していくべき理由として高々と据えられるべきなのだろうか。
「やさしく」「簡単に」ということは、たしかに必要かつこれからの社会において正しい道に違いないが、〝あなた方外国人が勉強するのはこの辺までのレベルでいいんですよ〟と見くびることになってはいけないはずである(シーズン1第9回)。筆者は細々と韓国語を独学的に学んでいるのであるが、韓国人ネイティブともしことばを交わすときに、「難しいでしょう?日本人のあなたはこの簡単韓国語を覚えればもうそれで OK ですよ」と言われたら、なんだか悔しい。旅行でいったときなどに、基礎的、日常的な韓国語が読めて、理解できて「おお、わかるぞ!」と思える満足感や安心感とはまた別次元の、ことばを習得する根本的なモチベーションにかかわることなのである。いわば、これは人間の学びのプライドに関わる話でもあるということを、忘れてはいけない。「簡単にすること」は、常に、どんなときでも、だれにでも、最善とは限らない。たとえばそれでしか学ばなかった人は、ネイティブの、「簡単」でないことばが飛び交う現場にはとても入れなくなってしまうリスクについてはどうだろう。もうここには格差ができてしまっている。何度も言うが、日本語の国際化とか、やさしいことばへの言い換えといったことの、根本理念は公平、格差解消にあるとみられる。ところが、実行に移すと皮肉にもそれが顕現したり、助長されてしまうかもしれない、そのリスクについての議論がまだまだ足りないと思う。
著者紹介
尾山 慎(おやま しん)
奈良女子大学教授。真言宗御室派寳珠院住職。
著作に『二合仮名の研究』(和泉書院、2019)、『上代日本語表記論の構想』(花鳥社、2021)、『日本語の文字と表記 学びとその方法』(花鳥社、2022)。
![]() シーズン2 第8回 漢字廃止へのまなざし——文字とことばの「国際化」とは(後編)
シーズン2 第8回 漢字廃止へのまなざし——文字とことばの「国際化」とは(後編)
![]() シーズン2 第6回 漢字廃止へのまなざし——文字とことばの「国際化」とは(前編)
シーズン2 第6回 漢字廃止へのまなざし——文字とことばの「国際化」とは(前編)