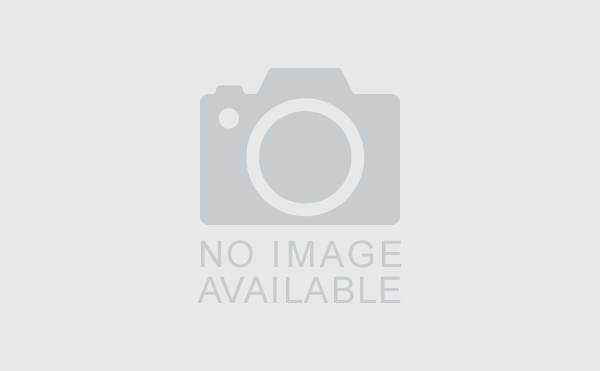シーズン2 第9回
感謝しかない
尾山 慎

コラム延長戦!「文字の窓 ことばの景色」。
定番フレーズへの違和感
「感謝しかないです」。この言い回しを目にしたこと、耳にしたことがある人はいまやかなり多いだろう。スポーツ選手が大きな大会で勝利を飾った直後のインタビューで語るとき、あるいは SNS 上で日常を振り返るときなどにも、いまや定番フレーズの一つになっている。たとえば「支えてくれた仲間に、家族に、もう感謝しかないです」といった具合だ。しかし、少し立ち止まって考えてみると、この表現には奇妙な響きがある。「しかない」とは本来、ネガティブな文脈で使われるものではなかっただろうか。宿題に追われる学生が、「もう徹夜でやるしかない」と嘆くように、「仕方なさ」「選択の余地無く選ぶ」といった意味がつきまとっていたはずである。そう考えると、「感謝しかない」というポジティブな感情表現は、どうにも収まりが悪い。

(画像は生成 AI による)
それでもこのことばが広がっているのはなぜか。真の出所(史上初めてこの表現を使った人、その瞬間)は知り得るものではないが、現状、SNS を中心によく使われていることは疑いない。そこでこの〝違和感〟を出発点に考えてみると、現代日本語の興味深い変化と、SNS という言語表現プラットフォームがもたらす、あるいは指向する、その文化の影響が見えてくる。
本来の意味――「窮余」と「やむをえなさ」
「しかない」という表現は、限定を意味する助詞「しか」+否定辞「ない」である。「A しかない」は「A 以外に存在しない」という意を表す。「一つしかない」のほか、行為にまつわる「行くしかない」のような場合は、「本意ではないが他に選択肢がない」という含意が読み取られやすい。「もう走るしかない」とか「謝るしかない」——共通するのは、「窮余(追い詰められて困り切ったあげく。苦しまぎれ)」「仕方がない」といった状況描写において結びついてきた表現という点である。つまりは、動作や心情にまつわる「しかない」とは主に、何らかの状況で、人がネガティブ状況に追い込まれたときに使われる表現であったわけで、この線から考えると、どう考えても「感謝しかない」は論理的におかしい。旧来用法でもし作文するなら、
「あれだけ長い間の付き合いで、いろんなやりとりをしたのに、感謝しかないの?ほかに示すことは無いの?不満も、悲しさも、苦々しさだってあっただろう?感謝しかないだなんて、そんなことあり得るかよ」
のようになるだろうか——無理矢理作ってみたが、どうにも変だ。実際、いま話題にしている「感謝しかない」は、こういう意味では、ない。
「感謝」とは「仕方なく、不本意ながら抱かされる」感情ではないし、「選択の余地なく抱かされる」ことでもなく、むしろ自発的で前向きに湧き上がる心情である。これにちなんでいえば、負の方向のことばである「不安しかない」や「憂鬱でしかない」は、広く調査をすれば、「感謝しかない」よりは、違和感が少ないと回答する人が多いのではないかと思う。
新しい用法拡張としての「感謝しかない」
動作や感情という観点でいうと、「泣くしかない」は行為を限定する表現であり、「感謝しかない」は感情を限定する表現ということになる。「感謝以外のことばでは言い表せない」という強意が働き、ポジティブな断定の効果を生み出している。ところで、上に、「感謝しかない」には違和感があると述べたけれども、あくまで「違和感」という程度であって、初見(初聞)で、意味が全然理解できないということはなかったと思う。この「耳慣れない(見慣れない)にもかかわらず、とりあえず言いたいことは直感的にわかる」というように、理解度の社会的関門を突破すると、ことばの意味用法は、したたかに新しい境地を開拓し、存在感を示し始める。比喩や文学的表現はそうやって新たな視界をもたらしてきた(だから、言い換えると、意味が二重になったり、割れたりする場合は広がりにくい。以前、「家事ハラ」ということばがそこまで広がらなかったことを意味の二重性から指摘した——シーズン1 27回「ハラスメント」あれこれ)。
SNS を見渡せば、「最高しかない」「尊いしかない」「癒やししかない」などの表現があふれている。いずれも「この感情以外、ない」と断定するスタイルであり、従来の「窮余」を逆手にとったような、強意的限定用法とでもいうべきものである。筆者は個人的に「最高しかない」などは使う気にならないし、相変わらず妙な感じがして仕方ないが、よくみると「最高しかない」は「【名詞】しかない」という点で、旧来の「弁償しかない」「裁判しかない」「一口しかない」と同じである。もちろん新用法の「感謝しかない」とも文法的には変わらない。「尊いしかない」も「尊い」が名詞相当になっているとみられる。このように、逸脱した使い方ではあるが実際は旧来から存在した用法の拡張でもあるというのは、つまりは、根本的な文法的違反(非文)ではないということでもある。
本来の性格からの逸脱・拡張として
上にも述べたように、文法的に見れば「しかない」は「限定+否定」であり、その根底には「やむをえなさ」がある。今一度確認しておくと、
「もう行くしかない」
「謝るしかない」
など、いずれも〝できれば避けたかったが、もう他の選択肢がない〟である。この構造を踏まえると、「感謝しかない」はやはり、旧来の表現に比して、逸脱だといわざるをえない。感謝という能動的で前向きな感情と、「しかない」のもつ、「致し方なさ」のような意味がそぐわないという、この両者間の齟齬をもって「変だ」「しっくり来ない」と感じる人がいると説明できる。しかし、違和感があることを起点に、この表現は間違いである、廃絶すべきであるという方向に話をもっていくのは、妥当ではない。現に日本語表現でこれほどいま当たり前になりつつある以上、この表現を成り立たせている構造や背景を見通すことにこそ、言語学的なアプローチの使命がある。そこで、「それ以外ない」という決め打ちのような判定をするということをキーに考えるとすると、参考になるのが、「レッテル貼り」というものである(笹井香「レッテル貼り文という文」(『日本語の研究 』13、2017)。笹井氏は「ばか者!」「嘘つき!」といった発話を「レッテル貼り文」と呼び、相手を単一のラベルに還元する文型として分析した。以前、ことばの暴力性というのに触れたが(シーズン1 30回 ことばに込めること、ことばを投げかけること——文字のスゴイ機能)、何かを描写する、人間の発話そのものが、本来的に対象にレッテルを貼る行為だともいえるのである。
そこでだが、「感謝しかない」もレッテル貼りと同じ構造をもっていると見ることはできないだろうか。実際には「嬉しい」「驚き」「安堵」など複雑な感情が混じっているはずなのに、それらをそぎ落とし、ただ「感謝」という一つのレッテルにまとめてしまう。つまり罵倒のレッテルが否定のエネルギーを持つように、「感謝しかない」は肯定、賛意、好感のレッテルとして、強いエネルギーを発揮するわけである。自分の(本来、高度に多様であるはずの)心情・感慨を、排他的にただ一つ「感謝」とのことばで代表させて析出し、ラベリングしてしまうのである。その時、「しかない」はそのラベリングを強く実現することばだ。人の性格、人柄、そのときの情感などは多種多様であるのに、「この馬鹿野郎」「こいつは最低だ」と言ったりするように、レッテル張りとは、まさにことばのもつ暴力性の顕現である。
言語表現の貧困化
話を冒頭に戻すと、優勝したその選手も、大会当日までに、家族、チームメイトとは実際には様々な感情の交歓があっただろうし、中には負の感情もあったに違いないが、「感謝」の一言だけをもって、なおかつ「しかない」と添えることで、〝それ以外ナシ〟という一枚のラベルにしてしまう。実に、わかりやすいといえばわかりやすい。「感謝します」も、言語による感慨の表明であるが、それよりも「感謝しかないです」が強烈なのは、「ほかにはなにも言うべきことがない」ということを、バックスクリーンのようにドンと据えて強調できる点にある。これは感情のレッテル貼りですと宣言しているようなものだ。「感謝」という語の意味がプラスの意味にそもそも振れているので、「それだけ」という択一性を示すことで、程度の高さは、実にお手軽に、一気に増幅される。
この一連の構造は、皮肉な言い方をすれば、〈本来複雑多様であること〉を〈たった一言で代表させて、すませてしまう〉という言語表現の貧困化だともいえると思う。こういったことがもし常態化すると、言語による表現や理解が、社会的に栄養失調のように弱体化してしまうのではないか。なんでもかんでも「ヤバイ」「尊い」で片付けてしまう(あるいは、そのことばしか出てこない)のに通じるものがある(三宅香帆「推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない——自分の言葉でつくるオタク文章術」(ディスカヴァー・トゥエンティワン、2023)はこれに関連して面白い一冊である)。
この「レッテル化の快感」「キャッチーで瞬間的増幅の効果」が期待できるというそのお手軽感は、少し語弊があるかもしれないが、まるで感情表現のドーピングのように思われる——繰り返すと摩耗するのに、しかし、いつしかそればかりに頼ることになる——。
選手が、お立ち台で発言するようになるより先に、文字世界つまり SNS で先行してこの表現は存在していたとみられるが、複雑な説明よりも、一言の断定が共感を呼びやすいのは SNS 界のもはや不文律となっている。レッテル貼り的な短い表現は、ネット空間において最も流通しやすいフォーマットである。そしてこれが、いまや対面の現実世界の談話(自然会話のこと)にも浸潤してきているというのが実情だろう。
SNS 文化と共感の仕組み
SNS のコミュニケーション様式を顧みると、まず第一に、投稿とは「短い」というのがある。限られた文字数で感情を伝えるには、複雑な説明を省き、強い断定、択一的な結論に集約する必要がある。「感謝しかない」は、余計な説明を切り捨てる即効性のあるラベルとして大変機能的なのだと思われる。第二に、SNS では「共感」が最重要の価値である。投稿する人々は、基本的に自分の体験を共有し、他者から「いいね」や反応を得ようとする。そのとき、「感謝しかない」と短く断定すれば、他者もまた「わかる!」「いいね!」と即座に同調しやすい。短い断定に対しては、同じく短く断定的に同調してもらいやすいだろう。そういう意味での阿吽の呼吸が成立しているのだ。第三に、拡散の仕組みがある。断定的でシンプルな表現は引用・リポストされやすい。「~に感謝しかない」は拡散に適したことばとして定着していったと見られる。こうした背景を考えれば、「感謝しかない」は単なる流行語ではなく、SNS の言語文化そのものを反映したことばだと理解できるのではないか。
「感謝しかない」という表現は、逸脱であると同時に、完全な文法的違反でもない、言語の表現力を拡張した新しい用法である(と言わざるを得ない)。逸脱と拡張という両者のあいだで揺れ動くその姿は、現代日本語のダイナミズムを体現しているかのようだ。「レッテル貼り文化」と呼応しつつ複雑な感情をそぎ落として一語で、かつ排他的に断定することへの快感や説得力(それは特に錯覚だが)と、まさにその即時的理解・即応的共感を欲してやまないネット・SNS 文化とが、見事にマッチングしたその申し子のような存在の表現だと思う。
以上のような構造と経緯でもって「感謝しかない」はいま、世を席巻しつつあるのではないだろうか。こう考えると、「感謝しかない」は正しいか誤りかで単純に片づけるべき表現ではなく、むしろ、ことばが社会の変化をどのように映すかを考えるうえで格好の素材であるといえるだろう。
著者紹介
尾山 慎(おやま しん)
奈良女子大学教授。真言宗御室派寳珠院住職。
著作に『二合仮名の研究』(和泉書院、2019)、『上代日本語表記論の構想』(花鳥社、2021)、『日本語の文字と表記 学びとその方法』(花鳥社、2022)。
![]() シーズン2 第10回 学術研究という「総合病院」
シーズン2 第10回 学術研究という「総合病院」
![]() シーズン2 第8回 漢字廃止へのまなざし——文字とことばの「国際化」とは(後編)
シーズン2 第8回 漢字廃止へのまなざし——文字とことばの「国際化」とは(後編)