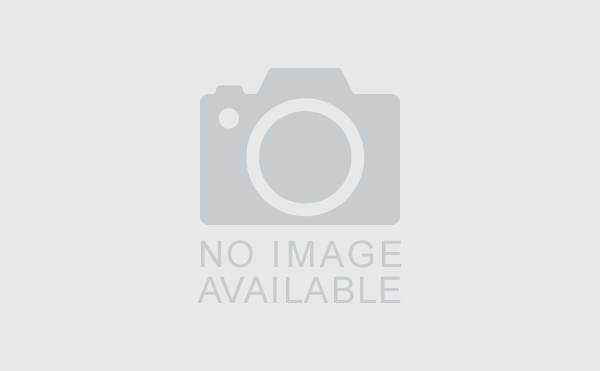シーズン1 第28回
瞬発的思考と熟慮・熟考
尾山 慎

コラム延長戦!「文字の窓 ことばの景色」。
瞬発力が勝負
まずはこの問いから始めよう。禅問答である。
「父(母)と夫(妻)が溺れている。どちらを助けるか」
問答の答えは「手前にいる方を助ける」。ぱっと答えないといけない。どうだろう?この回答に、おおなるほど!と思えるだろうか。まずさっと取りかかれて、成功する確率が高い方に迷わずいけ、ということを教えている。お寺のお堂などで、お坊さんからこの話を説法として聞くと、とりあえず「いやぁええ話聞いた」などと納得できる……かもしれない。が、その一方で、次々と、「でも、、、」といろいろ言いたくもなってこないだろうか。つまり、冷静に考えるとあれこれ「ツッコミ」をいれたい!——いまもうこれを読んでる側から、うずうずしている人もいるかもしれない。そしてそもそも、これは「我がこと」として考えるべきことなのか?そこも考え所である。
いろいろ考え得る〝反論〟〝意見〟を挙げてみよう。
◎「どちらを助けるか」がまず誘導的だ。両方助けるにはどうしたらいいかと考えるべきではないのか。
◎手前にいるほうが助けやすいとは限らないのではないか。
◎「どちらも助けない」はあってはならないことか?夫婦関係、親子関係は人それぞれ。人間関係というのは生々しい。
◎夫・妻は泳げないが、父・母は泳げるので、父・母が手前にいても、奥の夫・妻を救うべき、というケースもあるのでは?
◎ふつう配偶者のほうが若く、親はそれより年老いているのだから、どこにいようが親から救うべきでは?
◎親は老い先短く、配偶者はまだ未来があるので、配偶者を救うという人もいるかも。
◎自分が溺れるかもしれないというリスクマネジメントはどうなっているのか。
◎助けを呼びに行く、応援を求めるという選択肢は?高波はすぐそこまで来ているとか。3人とも死んでは何もならないじゃないか。
◎飛び込む前に、周囲に浮き輪や、つかまれるもの、ロープがないか探すということは?浮き輪が2つあれば一気に助けられるかも。
◎そもそもなんで2人揃って溺れているんだ。
まだ他にもあるかもしれない。鋭い指摘から言いがかりに近いものまで様々だが、いずれも、「この問答にそもそも異議あり!」という具合に、挙げてみた。もちろん、当然ながら問答においてはこういうツッコミ類は全く意に介されない(意味をなさないし、そもそも異議申し立てするタイミングもない)。細かい設定はないのである。ちょうど算数の問題で「弟は兄が出発してから5分後に分速80m の速さで1500m 先の駅に向かいました、弟が兄に追いつくのは……」みたいな問題で、「そもそも兄貴は、弟を待ってやれや!」などとツッコむ空しさに似ている。
問答では聞かれたことに、できるかぎり普遍的な最適解を、最短の時間で答えること自体に意味がある。言い方を変えれば、「あなたの親が」とか「あなたが海辺にいるとき」という個別的設定で考えるわけでは、必ずしもないということだ。とはいえ、冒頭の「問」を見て、「あなたの」とは言っていないものの、やはり、まずは我が身のこととして考えた人は多いと思う。が、実際は、ごく抽象的でいいのである。むしろ、我が身に置き換えると、「うちのお父さんは泳げるけど、旦那は水泳苦手だったよなぁ……」などと、具体的に考えてしまう。この天秤に掛けている時間がすでに勿体ないわけで、「ああでもない、こうでもない」が、ロスになる。
いまこの、「ああもいえる、こうもいえる」「……かもしれない」「……じゃないかもしれない」「こうも考えられないだろうか」といった様々な多角的、複眼的思考を、「可能性的思考」と仮称することにしよう。まさに熟慮・熟考することである。それに対して、あれこれ思い悩まず、これだ!とばかりにたった一つの答えを瞬間的、直感的に導いて決めるのを「瞬発的択一解答」と仮称しよう。問答は、基本的に後者を求めるのである。が、前者の思考に慣らされていると、短い時間でぱっと決めて回答する、ということに、なかなか抵抗がある。
筆者は大学生時代に夏目漱石の漢詩を研究する授業にでていたのだが、漱石が読んだとされる『禅林句集』とか『碧厳録』といった禅の教えを説いたものを調べる必要があった。そこでは、基本的に、ああもいえるこうもいえる、ということではなく、ずばっ!と解答を出したり、行動に示したりするので、気持ちいいといえば気持ちいい話、納得できないといえば全く納得できない話が沢山あった。ちょっと不思議な世界ですらあるので、是非一度手にとって読んでみていただきたい。「えええ?」と驚くようなエピソードが満載である。
もっとも、世の中には人より何十倍もの速いスピードで「可能性的思考」を回したあげく、端からみると「瞬発的択一解答」をしたかのように瞬時に答えるという超人もいるのだろうが、どうせそんな人は滅多にいないので、そういうすごすぎる人はいま横においておこう。〈熟慮に熟慮を重ねて、択一的な明言を避ける、あるいは時間をかけて仮説をいくつかたてつつ、じっくり回答を導く〉のと〈直感で、短い時間で、ある一つの解を即答〉くらいの対比だと思って頂きたい。
可能性的思考と瞬発的択一解答
この禅問答的応答のあり方について、「可能性的思考」の立場から様々にツッコミをいれるということに、(問答の側からすれば)意味がないと上に述べた。しかし、もちろん、疑問や異論を持ってはいけないという意味ではない。それはそれで「アリ」だ。それに、実生活や学校教育では、どちらかといえばこの「可能性的思考」こそ奨励されているのではないか。いかにそれを訓練するかが腐心されているともいえよう。「短絡的に考えるな」「勇み足」「早とちり」などという戒めのことばがたくさんあるように、立ち止まって、さまざまに考えることの意義が繰り返し説かれる。Xでバカな内容の投稿をしてしまう前に一呼吸おいてもう一回読みましょう、などというのはその啓蒙の典型的な一つだろう。ヨシタケシンスケ氏のベストセラー絵本『りんごかもしれない』(ブロンズ新社、2013)は、こどもたちをそういった思索世界に浸らせる(そのような思索の態度がある、ということ自体を知る)傑作のひとつだ。
ただ、その訓練が熟達してくると、時間を掛けた「可能性的思考」をせずにすぐ一つの解をはじきだすことそのものに否定的、あるいは、やってはならないことのように捉えてしまうかもしれない。つまり、「可能性的思考」が得意な人、習慣として染みついている人ほど、「瞬発的択一回答」的な答えの出し方に眉をひそめる、ということだ。そんな一発決め打ちのような決着で良いのか?早く答えを出せばエライのか?などと胡散臭く思ってしまう。それこそ「短絡的」「考えが浅い」といった具合に。しかしこれは、結果として、もう一段階上位(メタ)としての、「可能性的思考」——物事には様々な考え方、捉え方がある、ということそれ自体を、他でもない自らが否定し、潰していることになりかねない。ということは、すぱっと一言、これだ!と決め打ちする回路があったっていいじゃないか、ということである。それを認めてこそ、〈可能性的思考〉の意義も、光るというものだ。
ところで、今日、テレビや youtube などでは、すぱっ!とこれで決まり!という答えの出し方が、むしろよくもてはやされているという流れがあるのは事実だ。禅問答と一緒にはできないが、しかし「~だけで OK」とか、「これすぐ決断できないのはバカ」といった具合に、もうたった一撃、たった一手で済ませて、他の議論を許さない類いである。「一言でいうと」というフレーズも、界隈によってはこちらがもてはやされる。ネットニュースの見出しなどでよく「ぴしゃり」「ばっさり」といった擬態語とともに、快刀乱麻を演出する記事(の見出し)を目にすることも、そういえば多い(が、大して「ぴしゃり」でもなかったりするけれど)。どこかで皆そういうものへの憧れやすっきり感を味わいたい願望はあるのだろう。「可能性的思考」、とくにそのプロセスをひたすら見せるというのは、確かに全くテレビ的ではない。討論会という、まさにああもいえるこうもいえる、というのを見せる番組であっても、手早く回す、手短にまとめる、一言で言うと?と煽る司会者がいるほうが、テレビ的ではあるだろう(このことをめぐる問題は次回、詳細に考えたいと思う)。
それぞれにふさわしい場面がある
ある、テレビにでている脳科学者は、沢山の説があって、定説はないとことわっているのに、「3分以内で分かりやすくひとつだけ説明してください」と番組ディレクターによくいわれるという。「諸説」なんていらないのである。3分どころか1分もないこともざらだとか。発する方も大変だが、受け手にしても、こういう類いの情報発信にだけ慣らされていると、どういうことが起こってくるのだろうか。本当に短絡的で浅い意見に追随してしまうのは恐ろしい。そういう言説から知的に自らを防衛をするためには、「情報リテラシー(可否判断の正確さ)」を磨くことと、「可能性的思考」を常時癖にするのが、結局は唯一に近い方法だ。ということはやはり、学校などでも奨励される方向性へと戻ってくるわけで、「可能性的思考」の鍛錬を繰り返す、で基本的に間違っていないと筆者も思う。が、それでも、択一的にすぱっと絞るという解の出し方の、存在自体までをも否定する必要は無いと思うのである。上に述べたように、それはそれで、見識の幅が狭まってしまいかねず、よくない。
なぜ、問答が「(自分にとって大切な人が)溺れている」と問題設定したかと考えると、おそらく「差し迫った状況で、瞬時の判断を求められる」という状況を作るためだろう。「配偶者と親が、「肩を揉んでくれ」といっている。どちらを揉むか?」では問答にならない。
悩んでいるうちに2人とも溺れて命を落としたのでは何もならない。こういう切羽詰まった状況は、人にしばしば降りかかる。悠長なことを言ってられない時の択一的判断力も、重要なのだ(先ほど触れたが、一瞬にちかいほどで可能性的思考を通過して絞り込んで決断に至れる人もいるかもしれないが、きっと一握りだろう)。
ということで、このようにある問いに対する、解の出し方には、瞬発的に一つに絞る、〈瞬発的択一思考〉と、〈可能性的思考〉の両方ありうる(あっていい)——このことを踏まえて、次回はいま流行りの「タイパ」「コスパ」ということを、ことばや文章の読み書きという観点から考えてみよう。思考のありかたとしては両様あっていいと思うが、時間の節約、短い時間で大きな効果をえられる、満足できる(それはイコール、時間がかかるのは無駄、不利益)ということだけが、暴走的に志向されると一体どうなるのだろうか。
著者紹介
尾山 慎(おやま しん)
奈良女子大学准教授。真言宗御室派寳珠院住職。
著作に『二合仮名の研究』(和泉書院、2019)、『上代日本語表記論の構想』(花鳥社、2021)、『日本語の文字と表記 学びとその方法』(花鳥社、2022)。