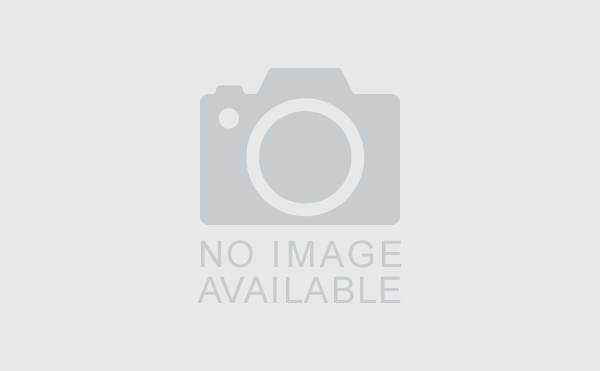シーズン1 第29回
タイパ・コスパの果てに
尾山 慎

コラム延長戦!「文字の窓 ことばの景色」。
「一言でいうと」
学生時代、ある講演会で、結構難しい経済学の話を聞いたことがあった。講演後の質疑に入る前に、司会者が「先生、今日の要点を一言でいっていただくと?」と切り出した。難解だったので、正直、筆者はその答えに期待した。司会者もこのままでは会場からの質問がでないと思ったのだろうか——だから決して悪気はなかったと思う。が、講師先生は不愉快に思ったのか司会者のほうを向きもせず(これにはちょっとひやっとした)、しかし声を荒げることはなくむしろ落ち着いた声で、「一言で言えないことだから90分こうして話してきたわけですが」と返した。本音だろうし、正論だろう(と、これは今の筆者の感想)。もしかしたら講師先生はこのストレートな返しが〝ウケる〟と思ったのかもしれなかった——が、実際には、思い切り会場は静まりかえってしまった。そのとき、筆者達(聴講者)を見据える先生の表情が少し戸惑いを帯びたように見えたので、もしかしたら「ありゃ?! みな引いちゃったか~」と思ったのだろうか、今度は司会者のほうに向き直りつつ、「いやいや、今日、実は、半期掛けて大学で講義していることを90分にしたので、あちこち詰め込んで難しかったと思います、一言では……なかなかねぇ……」とそこではじめてすこしはにかんだような顔をされ、辛うじて会場の温度もじわじわ回復しはじめた。司会者も大仰に手を振って、いやいや申し訳ございませんっ!などとまくしたてて、そこからなんとかうまく立て直して、結局それなりにつつがなく質疑も進んで、終わった記憶がある。
「一言でどうぞ」——このことばを、スパッと相手の答えを気持ちよく引き出す、魔法、万能の「フリ(仕向け)」だと思っている人がしばしばいる。が、それは概ね勘違いだろうと思う。これを使うのは遊びやゲーム感覚のおしゃべり中くらいにしておいたほうがいい。実にテレビ的というか、バラエティ風のキャッチーさがあるけれども、それだけにとりわけ面倒なのは、聞かれたほうがもし答えに窮すると、まるで頭の回転が遅い、とんちがきかないなどという扱いをされかねない、その圧が伴うという点だ。「一言でどうぞ」、それこそたった一言投げかけるだけの側が、圧倒的優位に立つというズルさがある(従って上記講演会の出来事は希なケースだろう)。ということで、この「一言で」は実際、いろいろな場面で、魔法、万能どころか、ほとんどがただの「無茶ぶり」である。たとえば、桃太郎を一言で説明してくださいといわれて、答えられるだろうか。答えたとして、それでよしとできる合意はどうやってとるのだろう。もっといえば一言でいわせてなにになるのか。ちなみに筆者は試みに、無茶と承知で聞くのですがと学生に尋ねてみたことがあるのだが、桃太郎を本当に一言で、というと多くの人が「鬼退治」と答えた。では一文字でなら?ときくと、みんな「桃」だった(「鬼」ではない)。そこで、これをひっくり返して、「鬼退治」や「桃」の一言、一文字だけを手がかりに、桃太郎を読んで知ったことになるかというと、勿論、そんなはずもない。一言でいわせてなにになるのか?というのはそういう意味である。
件の、「一言でいえないから90分しゃべってきたわけですが」との返しに、会場は水を打ったような静寂に包まれることになったが、実は内心、そうだよなと快哉を送った人はいたかもしれない——今となっては、そう思う。
タイパ重視
タイパ——タイムパフォーマンスは、「いい」「わるい」、「重視」などといったことばと結び付き、費用対効果ならぬ時間対効果でよしあしが測られる。基本的には、合理主義、功利主義的な考えに裏付けられたものだが、実に現代的であり、かつまた資本主義社会に親和性が高い観念だろうと思う。時間は全員に公平に一日24時間だが、選択肢が膨大なので、実際、時間のマネジメントが、かつてないほど求められるところがあるのは事実だ。
広い目、長い目でみれば、たとえば東京—大阪間で新幹線や飛行機を使うのはまさしくタイパ重視であり、それは交通網、交通手段発達の歴史に重ねられる。電車の旅自体を目的とでもしないかぎり、在来電車を乗り継いで6時間も7時間もかけてふつうはいかない。しかし今日、大阪から東京への出張に新幹線でいくことを取り立ててタイパとはふつう表現しないはずで、社会的にほとんどの人がそういう選択をするようになると、特段タイパともいわれず意識されなくなる。いやそれどころかもっと早くならないだろうか、などと思ったりする。この飽くなき、むき出しの欲とでもいうべきタイパ・コスパ志向は、合理、功利という大看板を背にして、確かに文明社会をここまで切り開いて発展させてきた原動力でもあった。
ネットの情報によれば、タイパ重視とは Z 世代(若い人たち——所説あるそうだが、おおむね1992−2012年あたりに生まれた人たち)の新たな価値観とよく紹介されていたが、もとをただせば、そんな世代限定ということはないはずである。社会全体でそういう志向性はこれまでも普通にあったわけだから。ただ急速に、そして極端に顕在化してきたきらいがある、ということだろう。後から紹介するように、自分が見たくて選んだ映画であるにもかかわらず、2時間半は長い(=タイパが悪い)というのである。これには驚く人も多いかもしれない。
ただ、根本的に突き詰めれば、現代文明に生きる人間として、やはりタイパ指向、タイパ追求は否定できるものではないと筆者は思っている(それこそ、否定すると在来線よりも高い運賃を払って新幹線に乗ることの説明が付かない)。ただ、タイパ追求が行きすぎると、そしてそれだけが追い求められ続けると、どういうことになるのかについてはそろそろ考えて良い時期にさしかかっている。
稲田豊史『映画を早送りで観る人たち』(光文社新書、2022)は、セリフのない部分を中心に早送り(ほとんどすっとばしに近い)でドラマや映画を鑑賞する、ということについて様々な考察がなされている、大変興味深い一冊である。映画鑑賞、ドラマ鑑賞もいまやタイパという観点で向き合う対象になっているらしい。仕事ではタイパ追求するけれど、休暇やエンタメ体験ではゆっくり、のんびり、じっくり……では必ずしもないところに、今日的タイパ志向の病理が潜んでいるのではないだろうか。
2010年代後半~そしてとりわけ2020年以降コロナ禍で爆発的に利用者を増やしたネットフリックスやアマゾンプライムビデオ等々、いわゆるサブスク(サブスクリプションの略。月額や年額のような定額料金を支払い、一定の期間、商品やサービスを利用できるシステム)時代にはいると、動画再生に関する操作は自由自在なので、「すっとばし」は本当に手軽になった。たとえば全32話(のべ40時間を超える)のドラマの中を話数ごとにあちらこちら自在に飛ばしたり、戻ったり、一話の中でも早送り速度が2倍、4倍、8倍……とあって、さらには10秒前、10秒後などの操作も可能である。DVD だと、せいぜい一枚に2~3話しか収まらず、そもそもデッキから入れ替えないといけないから、その手間もあって現在ほどの自由さは、明らかになかった。ましてそのさらに前のビデオテープなどそんな細かいことはできないから(10秒戻しなんて繰り返していたらきっと機械が故障する)、映画、ドラマの「すっとばし」鑑賞は、そういう勝手気ままかつ非常に細やかな操作を可能にする技術、機器の性能と共に、相互に磨き上げられてきているといってもいいだろう。
それにしても、無言のシーンにも意味があるということなんてお構いなしにあっけらかんと飛ばされてしまうというのにはちょっと驚く。稲田氏が例に挙げるように、たとえばドラマや映画で、部屋に1人しかいないというシーンがあったとして、目の前の机にはグラスが2つあって、しかも氷が溶けていなければ、ほんのついさっきまでもう1人いたのだろうと推測するのが普通だ。そういう意味において、ことばはなくても、重要なシーンというのは随所にあるはずである。まさか、「さっきまでいたあいつが、いまはもういない」などと説明的なことを俳優にしゃべらせるほうが白ける。しかしこの調子で〝無言シーン飛ばし〟をやっていると、モノ(キーアイテム)が大写しになるシーン——たとえば、もみ合いの末にボタンが一つ落ちたとか、携帯がポケットからするっと落ちたのに気づかず出て行ってしまうとか、あきらかにストーリー理解や伏線、布石の把握に必要なことを視聴者に認識させる箇所——これらもほいほいと飛ばされてしまう可能性が高く、一体、それで本当にストーリーを読解できたことになるのだろうか、と心配になる(その程度の理解でいいと思っているといわれればそれまでの話だ。が、後述の通り、万事この調子になると様々な問題が発生してくると思われる)。
タイパとは、「費やした時間に対する成果、効果や満足度の度合い」などといわれるが、本当は満足なんて全然できるものではない状態なのかもしれない。読解結果は実はボロボロである恐れがある。それでも、いやいや満足したと本人が思えばそれでいいんじゃないか?といわれるかもしれないが、個人で楽しむエンタメ体験などならまだしも、それをも超えてこの感覚が、過剰に、日常ふだんや学業、仕事などにまで蔓延、浸潤してくるとなるとやはり危うい。〈時間かかるのはダサいし無駄!〉という慢性的な錯覚状態——これが集団的に起きていく、というのは、果たして杞憂であろうか。
タイパ・コスパ的文章読解の末に
前述の通り、タイパを求める感覚はだれしもあっても、あまりにとらわれすぎてあくなき追及を続けると、まるで〝強迫性タイパ衝動〟のようなものを引き起こすのではないかと危惧する。あるいはタイパ自体が目的になる(タイパはあくまで結果論であるはずなのに)。
タイパ至上主義が行き過ぎると、いったいどういうことが起こりうるか、文章の読解ということをサンプルにとってみよう。あらかじめいっておけばこれは非常に単純な予測である。一年365日毎昼ごはんをインスタントラーメンにすればきっと体によくあるまい。できるだけ歩かず、運動せず、夜は深酒を欠かさないようにし、睡眠は5時間以上は取らない、こうなればきっと、一年後の健康診断でとんでもない結果になるだろう——といった、そういうシンプルな予測である。
タイパ至上にとらわれると、もはやそもそも〈時間をかける〉というのが苦痛になってくるとまずは予想される。読むのに30分はかかる文章があるとしよう。しかしそこに、だいたいこんな内容だと箇条書き要点が5つほど抽出してあったら、それに飛びついて、しかも、それでもう理解したつもりになってしまう(実際の文章のほうはもう読まない)。ネットのヤフコメ(ヤフーのニュースなどに匿名でつくコメント)は、現在、AI が抽出した抜粋がまず表示される——いまのところ試験運用なのだそうだ。AI の要約が正鵠を射ているとは限らないのに要約しかチェックしなければ、〝AI 要約には拾われなかったが鋭い意見〟などは見出されるべくもないことになる。タイパはそうやって、実は潜んでいる「きらりと光る情報」を取りこぼすことと引き換え(トレードオフ)であるかもしれないのだ。
短くすること、はしょること、省略すること自体は以前からしばしばあることだし、ただちに〝いけないこと〟ではない。しかし、タイパにとらわれすぎてそれを目的にすると、やはりどうしても、時間がかかることを無価値、無意味にとらえる世界観をもたらすだろう。無価値ならまだしも、たとえば文章の読み書きひとつとっても〝時間を要することは有害〟だとまで考え出すと、いよいよ危ない。結果、長い文章を読むことを敬遠したり、あまつさえ、長い文章であること自体が悪いのだとレッテル貼りをしてしまったりする。「一言で言うと」「要点は次の通り」という抄出(抜き出し、抜粋)だけを参照して、もう分かったことにする。いや「分かったことにする」と自覚しているあいだはまだよくて、いずれ「分かった」と思い込むようになる——こういった、実に心配な〝症状〟が予想される。
長い文章を読めないのだから、必然的に長い文章を書けるはずもなく、結局読む力も、書く力も衰退するだろう。ネット上で、グルメやファッションの記事を書いてばりばり活躍されている方が、そのネットで発信する際の文章作成指南をするというサイトを見たことがある。そこでは、自分は、総じて3分以内で読めるものを心掛けている、とあった。ネットという戦場において商業的には理にかなっているのだろう。ご本人も、「私もネット記事で3分以上かかるものは、たいていそこで読むのを打ち切ります」と言い切っていた。それ以上は無駄だ、というわけである。
しかし、読むなら3分以内——こういう向き合い方を、ネット商売の説明文といったジャンルを超えて、あまり万事、四方八方に奨励すると、世の中には当然それ以上かかるものは山のようにあるから、そういった文章というものに向き合っても、「やめ癖」「くじけ癖」「3分でギブアップ癖」がつきはしないだろうかと懸念される。しかも、そういうときにもし「3分以上かかるのは長くて読めないし、理解もしにくいので、だいたいくじけます」というならこれは実に正直な告白だが、同じことでも、「善」たるタイパという御旗のもとに「3分以上かかるものは読むのを打ち切って OK!」と言い換えられると、なんだかそっちのほうがいかにも「デキる人」感が滲むし、やっぱそれでいいんだよねとさぞかし背中を押されることだろう。
あふれかえるコンテンツの中で
先にも少し述べたが、そもそも選択肢が多すぎるというのもある。我が家もネットフリックスに加入しているのだが、子ども向けでも、たとえば『クレヨンしんちゃん』『「ドラえもん」だけで常時のべ100話くらい用意されている。しかもそれが一定期間で更新されていく。つまり、延々と見続けられてしまうのだ。しかし、他にも見たいものはあるわけで、仕事や学校や睡眠ということを考えると、一日24時間どころか、一日50時間あったって足りない。いやそもそも見切る必要もないし、見切るという発想もしなくていいのかもしれないが。
スポーツといえば相撲、そしてプロ野球くらい、家族でひとつのテレビだけを見ていた時代があった。「チャンネル権」「チャンネル争い」という言葉を聞いて懐かしく思い出す世代と、「なにそれ?」という世代とに分かれることだろう。これらはほぼ死語になってしまった。一家に一台しかテレビがなく、そしてテレビ以外に視聴できる媒体がなかった時代が長らくあった。みんな同じ曜日の同じ時間に『ドリフ』や『オレたちひょうきん族』を見ていた時代——それはもうはるかな昔なのである。話題のバラエティ番組を見逃していたら、翌日学校で話についていけず肩身の狭い思いをしたという、主に40代以降の方々も少なくないのではないだろうか。いま小学生の息子にいろいろ聞いてみると、あまたのゲーム、アニメ、漫画、キャラクターなどに茫漠と囲まれているので、「俺、それ別に興味ない」とか「見てない」とかいっても、ただそれだけの話で、それ以上どうこうということはあまりないのだそうだ。そもそも「昨日のテレビの〇〇見た?」という会話がほぼないのである。見た?と聞くなら youtube だ。あるいはテレビ番組もオンデマンドがある。もし見てないといえばその場でタブレットで再生して一緒に見ればいい。その動画・番組を知らなかったことはいまや別に恥でもなんでもないのだ。すぐに見られるから。ものすごく選択肢があるなかでどれを選ぶかという話だから、「それあんまり知らない」といっても、さほど不思議ではないのかもしれない。
一日の時間だけはみな同じなので、その中でどれほどのものを選び取って、価値ある効果や満足を得られるか。タイパ重視というのは、たしかに今日的必然という側面はあらためて、あると言わざるを得ない。何せ、時間が足りないのだから。昨今、闇バイトというのが問題になっている。犯罪歴もないごく普通の若者がどうして?と思うが、ようするに、コンビニで時給1000円でこつこつ働くよりも、タイパ——一回実働一時間以内でウン十万円だと聞いて、俺はそっちでがっぼり稼いでやるぜ!と安易に応募してしまうのだそうだ。仕事内容が重大な犯罪だということが霞んでしまうほどに、タイパ・コスパ自体が目的になってしまっている如実な例であろう。お金のために犯罪というのは古今東西あるが、タイパ・コスパ志向がその動機を助長しているところがあるらしい。かように、もうすでに非常に良くない形で社会問題化してしまっている。従って、過剰タイパ志向(思考)なるものへの、社会的な内省・反省はもはや待ったなしなのである。
たまにはインスタントラーメンもいいと思う。たまにはお酒を楽しんでだらけるのも悪くはないかもしれない。それと一緒で、たまに、タイパ重視の読み方、見方でもいいだろう。要約、抜粋だけでもうよしとする、適当に早送りしながら30分程度で2時間ドラマ鑑賞なども、誰かから禁じられる筋合いは、基本的にはないとは思う。繰り返すように、忙しくて時間がないわりに、選択肢は膨大だから。しかし、いつでもどこでもそれではよくない、というか危ういのである。それが日常普段、普通(ディフォルト)にセットされてしまう、しかも個人を超えて社会がそういうありようをよしとしていく方向性は、明らかに、危険である。文章の読み書きということでいえば、少なくともその「たまに」を、正反対のほうにも——つまりゆっくり構えて、じっくりと何度も読み込む、読むたびに違う発見がある、といった経験を積むほうに、あててみてはどうだろう。
「忙中閑あり」というではないか。それに、「味読」といういいことばもある。これを、今一度、振り返りたいものである。
著者紹介
尾山 慎(おやま しん)
奈良女子大学准教授。真言宗御室派寳珠院住職。
著作に『二合仮名の研究』(和泉書院、2019)、『上代日本語表記論の構想』(花鳥社、2021)、『日本語の文字と表記 学びとその方法』(花鳥社、2022)。