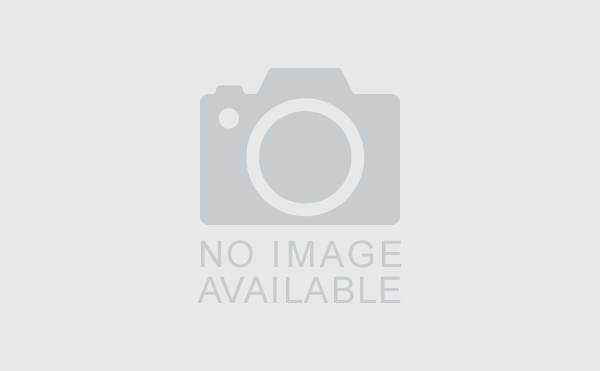シーズン1 第30回
ことばに込めること、ことばを投げかけること
——文字のスゴイ機能
尾山 慎

コラム延長戦!「文字の窓 ことばの景色」。
1文字が無限を包み込む
弘法大師空海に「真言は不思議なり(中略)一字に千理を含む」ということばがある(『般若心経秘鍵』)。真言(マントラ)とは、お寺のお堂でおまいりするときなどに見る、片仮名で「オン アビラウンケン ソワカ」などとかいてあるような密教の呪文をいう。空海は、「一字」といっているが、実際は文字とことば(つまり発音)を一体のものとしてここでは捉えていると思しい。その〈文字/ことば〉の、〈一文字/一音〉が指すことがら、内容の深遠さを、宗教者として賛嘆したものであり、真言宗においてはとても有名なことばである。たしかに真言をあらわす梵字は、単に文字記号というだけではなく、様々な意味があり、その梵字自体を仏と同じとみなして拝んだりするほどである(詳細は『日本語の文字と表記』収録コラム「文字の聖性 梵字の宇宙」参照)。なるほど一字に千理——本当に多くのことが込められているし、また教義としてもそれらを読み取る教えがある。ただ、このことは、実は宗教的文字やことばだけには限らない。そもそも文字やことばとは、普遍的にそういう機能をもっているのである。「千理」どころか、「無限」でさえも包み込んでしまう。
「無限」というのは実は単純ではない概念で、数学者の中でも論争がある。ふつうは終わりがないといったくらいの意味で把握されているだろう。そこでだが、〝終わりがないもの〟を何かに閉じ込めることはできるだろうか(変な質問だけれど)。箱のようなものがあったとして、その中身が、〝終わりがない〟となると、つまり、永久に蓋は閉められない=閉じ込められないということにならないだろうか。
無限とはなにか?——ヒルベルトホテル
無限とは一体なんなのか?簡単な話ではないぞ、ということを、たとえ話——それも「あれ?この話なんか変だな」と直感的に思えるおもしろい例を使って説明した人がいる。ヒルベルトという著名な数学者だ(ドイツ、1862-1943)。通称「ヒルベルトホテル」という話である。
ここに、人数が無限に泊まれる「無限ホテル」がある。そこに、奇数様ご一行がやってくる(交通手段も無限席数のバスかなにかというところだろう)。奇数は当然無限である。無限だが、ホテルの部屋数も無限だから問題なく、無事にチェックイン、入室する。無限ホテルに無限人数が泊まるのだから、必然的に満室になるはずである。ところが、次に偶数様ご一行がやってくる。ホテルのフロントに、今日泊まれますか?空室ありますか?と聞く。ホテル側は即答する——「もちろんです!せっかくなので、奇数様との間、間へと入っていただきましょう」。ということで、「1さん」だけそのままに、「3さん」以降は一室あけては隣の隣へ、と移動してもらう。そしてその一つおきに空いた部屋に、偶数様が順に入室していく。偶数様ご一行もこうして無事チェックイン、入室完了である。偶数も無限だが、そもそも部屋数が無限なので問題ない……。いやいや、なんか変じゃないか?、この話??そもそも奇数様ご一行の時点で満室だったのでは?無限ってどういうことだ?——と、こういう具合に疑問を投げかけるのである。
もうひとつある。三角形を書き、頂点から下辺にむかって線を引く。引けるだけ引き続ける。当然、線と線との間はどんどん狭くなるだろう。物理的には書けなくなる限界があるが、理論上は、どんどんいけるはずだ。さきほど、「無限」を箱に閉じ込められるか?中身が無限だと蓋ができないのでは?という話をしたが、反対に、箱(つまりは閉じられた空間内)の中を無限に分割することはできるだろう。三角形の内側には、理論上、無限に線を引ける(図A)。

図A
分割は永久に細かくなっていく。そこで、図B をみたとき、切り口①と切り口②は、無限の分割線にたいして、2箇所の線を引いて切っている。このとき、①と②は、同じといえるか?幅違うよね?——と、このように無限なるものに、疑問を呈すわけである(以上の話には批判も勿論あるが、ここではこれ以上踏み込まない)。ともかくも「無限」はなかなか奥が深い。

図B
無限を閉じ込める数学記号
話を戻そう。「無限」は閉じ込められるか?との問い。ほかでもない文字こそ、それが可能だ。数学の記号を文字といってよいかどうかという問題はあるが、たとえば「π」は、円周率を閉じ込めている。円周率は無限に続くが、この1文字に全部入っている。無限なのに、全部入っていることにして、話を進められるわけである(これができるから数学は進歩した)。もっとすごいのもある。それは「Σ」(シグマ)である。シグマは、指定した数値に到達するまで、数字を全部足す、という記号で、下図の場合、1+2+3……で100まで順に足していけ、ということを表す。

さらにすごいのは、この、どこまで足すか(Σ記号の上部の数値)を、「∞」(無限)に設定することもできるのである。

n が1から始まって、
無限に足し続ける、の意
これを無限級数という。円周率 π のようなただ単に無限というだけではなく、なんと無限に足し続けていくことまでをも、たったこれだけの記号で、包み込んでしまえるのだ。数学では、有限ではなく無限大になることを「発散する(diverge)」という(ちなみにマイナス、負のほうへ(つまり減り続ける方向へ)の「発散」も勿論ある)。
あえて俗な言い方をしたいが——筆者は、こういうことを知るにつけ、人間が発明した文字、記号というものは、〝えげつない機能〟をもっているとおもう。人間は知能の発達によって抽象思考能力を手に入れたが、その相棒である記号もあわせて発明してしまった。記号化できるので、またその抽象思考が磨かれ、進展するのだ。古代エジプト人が、文字は神が発明し、その神からの授かり物だと考えたのも頷けるではないか(詳細は『日本語の文字と表記』第二章Ⅱ)。
神も閉じ込められてしまう
キリスト教の前身、ユダヤ教では、神の名をみだり唱えてはならない、という(モーゼの十戒)。「みだりに」というのが大事で、気軽に、軽率にいうものではない、ということだ(だから厳粛に祈りをささげるときなどは、キリスト教でも呼びかけることはあるのはよく知られているだろう——マタイ福音書「天にいます私たちの父よ。御名が聖なるものとされますように」など)。
「みだりに」ということもさることながら、そもそも「神とは~」と定義、規定するようなことも慎まなければならない。ことばは対象をパッケージにしてしまうことなので、神の名を呼んだとき、神が、そのパッケージに入ってしまう形になる。あなたが「神とは……~~である」と語るとき、そうしてパッケージにした神なり神の振る舞いを、まるで我が手中にして、そして上から眺めているような構図になる。いわゆる「メタ」視点で神をとらえる形になるわけで、己の認識内に、包摂してしまうというわけだ。
聖書の時代に、言語学はまだないけれども、みだりに神の名を唱えるな、というのは、宗教的に不敬ということはもちろんだろうが、ことばとはどういうものかということも、よくよく知られた上での戒めではないかと思われてならない。
ところで、神に限らず、「あなたは~だ」という規定めいた言い回しは、そもそも失礼にあたる。「あなたは本当に美しいですね」はどこからどうみても褒めことばだといわれるかもしれない。しかし、ことばのもつ働き、機能としては、悪口と実は一緒である。こどもに「えらいね、おりこうさん」というのは、褒めているがしかし、評価でもあって、そういう意味では「ほんまアホやな」といっているのと構造としては同じなのである。人を面と向かって評価するというのは善悪どちらでも、レッテルを貼るのと同じになる。つまり、「美人」「男前」「えらい」「アホ」などと書いた付箋を相手のおでこに一方的にぺたっと貼るようなものであって、ことばの語義としては褒めるものでも、行為としてはそういうものだと思っておいたほうがよい(だからまして罵倒語を直接浴びせるのなんて、とんでもない暴力なのである)。こうして考えると、人を褒めるのもなかなか気を遣うべきものだとわかる。「美人だね」といったってセクハラにされてしまう時代、などと嘆く声を聞くことがあるが、「褒めことばなんだから100%善意だけ」というのこそ、結構危うい考え方である。というかそれは、ことばというものの機能と働きについて、根本的なところで誤解があるといわねばならない。
面と向かっていう、なんらかの尺度を一方的にあてる失礼さということに鑑みれば、「美人」だろうが「かわいい」だろうが、不快に感じる人がいてもおかしくないのである。
ジャン=ジャック・ルセルクル(フランス、1946-)は、次のようにいっている。
発話行為の内には暗黙の要求がある。そして発話はどれもみなこの意味において発話行為である。(中略)ある女性に向かって「お前は私の妻だ。」と言うのは、その女性に妻の立場に伴うあらゆる義務を課そうとし、話し手自身には対称的な夫の立場に伴う義務や権利の数々を要求することである。「私はあなたを愛している」ということばを口にするのは、個人間のやりとりにおいて話し手と聞き手がともにそれぞれある種の立場を占めるのを要求することと全く同じようにである。
(岸正樹訳 『ことばの暴力 「よけいなもの」の言語学』法政大学出版局、2008)
発話して投げかけることには、基本的に暴力性がある、という見方である。どうだろう、なんと悲観的で窮屈な、とおもうだろうか。こんなことを気にしていたら何もしゃべれないじゃないか、と嫌気がさすだろうか。なるほどそうかもしれない。しかし、知っておくことは大切だとおもう。先にも述べたように、「あなたは本当に美しいですね」ということを、純度100%のプラス感情しかない、善意しかない、言われてイヤなはずがない!と心底信じて疑わず発するのと、時に、このようなことばはレッテル貼り、暴力にもなりうると知っているのとでは、全然違う。知っている上で、しかしここは褒めたい!称賛したい!とおもっておもわず発する、それでよいのだろうとおもう。
ことばのもつ力は、対面のみならず SNS などのコミュニケ―ションがさかんなこれからこそ、それぞれが互いに知っておきたいことではないだろうか。
著者紹介
尾山 慎(おやま しん)
奈良女子大学准教授。真言宗御室派寳珠院住職。
著作に『二合仮名の研究』(和泉書院、2019)、『上代日本語表記論の構想』(花鳥社、2021)、『日本語の文字と表記 学びとその方法』(花鳥社、2022)。
ありがとうございます。
今秋、ここまでの連載分をまとめ、書き下ろし数編を添えて書籍として刊行の予定です。
引き続き、おつきあいいただけましたら幸いです。