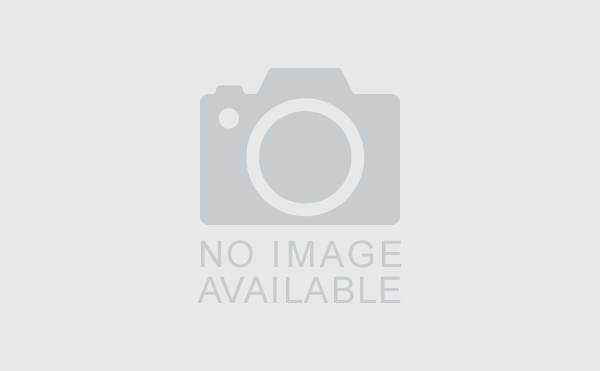シーズン2 第1回
認識とことば
尾山 慎

コラム延長戦「文字の窓 ことばの景色」。
シーズン2がスタートしました!
世界の見え方
ことばの機能は何か?と聞かれると、多くの人はコミュニケーションと答えるだろう。もちろんその通りだ。その一方で、自分自身の思考を整理したり、内省したりということにもことばは役立っている。では、この二つの大きな働きは、どちらが先なのだろうか。つまり、人は、コミュニケーションを通してことばを発達させたのか、それともことばによる内省で認知を明確にして、結果、より豊かなコミュニケーションを促したのか。
おそらく、どちらが先ということは言えない(というかあまり、決める意味がない)。両方、相互影響しながらというところだろう。人類史の解説などでは、ホモ・サピエンスが協働して大きな獲物を狩った、そのときにことばが非常に大きな役割を負ったという説明がなされることが多いが、たんに「こっちだぞ!」とか「俺が先回りするから!」といった連絡事項だけではなく、ことばで抽象的なことを考えたり、整理したり、まだ起きていない出来事や、目に見えないことを相談したり、相互に了解したりするためにもことばは当然役に立ったことだろう。コミュニケーションと内省(抽象思考)は、ことばという手段によって、両輪のように連結されて、発達してきたのだ(シーズン1 第12回 「この世のどんなものより」と言われて)。
そして、結果として、この世界の見え方はことばによっているところがある、という考え方が、よくなされる。有名なのが、「サピア・ウォーフの仮説」というものだ(2人の、言語学師弟による理論)。たとえば、「机の上に腕時計がある」とは言うが、「腕時計の下に机がある」とはいわない。事実としては正しいのに、そうは言わない(そういう言い方を決してしない、とするのが正確だろう)。それはつまり、私たちの世界の見え方のあらわれだ、というのだ。客観的に、公正に、歪みなく見ているつもりでも、注目するポイント、私たち人間の認知のクセのようなものがある。どうしても目がいくもの、注意がむくもの、というのがある。人間と動物なら人間に、大きいものと小さいものなら大がベース(背景)に、動くものと動かないものなら、動かないものがベース(基礎)に、といった具合である。たとえば、となりの空き教室に、チョークの箱があるから取ってきてくれない?と頼まれていってみたところ、誰もいないはずが猫がいたらちょっと驚くだろう。そして「猫がいました!」などと報告したりする。認知的にそこが際立つのである(そして肝心のチョークを持ってくるのを忘れてしまったり)。先に、腕時計の話をしたが、「家の前に自転車がとめてある」とは言うが、同じ現実でも、「自転車の後ろに家が建っている」とは普通言わない。自転車は家に比べて小さくて動くから、これを基準にして語るのは奇妙な気がするのだろう。しかし、「高層ビルの裏に学校がある」は、「学校の裏に高層ビルがある」とひっくりかえすことができる。両方とも大きくて、動かないから問題がないのだと考えられる。なるほどことばは、私たちの世界の見え方に深くかかわっているようだ。
一方で、ことばが完全にわたしたちの認知を支配しているというのはおそらく言い過ぎである。たとえば代表的なのが色だ。色の違いだけ、ことばがあるわけではない。そして、ことばがないからといって色の違いを区別できないわけではないし、第一、色は本来、切れ目がないグラデーションをなしているから、つまりは連続的だ。温度のイメージを冷から暖へ帯のように色でしめすとしたら、青から緑、黄色とかわって赤にいたる、という一続きで示されるだろう。
「半分も」と「~半分しかない」の違い
こういった領域から言語を考える学問分野を、 認知言語学というが、その初学書がよく導入で使う例文がある。
「ワインが半分も残っている」
と
「ワインが半分しか残っていない」
の違いである。フルボトル750㎖ のビンに、375㎖ 残っているという事実は同じであっても、それをことばでどう記述するか。私たちの思考、向き合い方、そしてそれを表明することは、時と場合によってさまざまである。言い方をかえれば人間は、事実を事実としてだけ受け取るのではなく、ことばで記述して(記述したものを解釈して)はじめて受け入れているともいえるのだろう。となると、当然、上の例文のように「~も」や「~しか」が含まれない、
「750㎖ のビンに、375㎖ 残っている」
とだけ言うとしたら、この一文については、価値付け、意味づけは、ほぼ押さえ込まれている、ごく客観的で、無色透明の文章といえるのではないだろうか。たしかに文章表現というレベルで対比的に、「~も」や「~しか」と比べていえばそうだが、結局、残量を記述する(言語化する)ということそれ自体が、すでに、事態に対する向き合い方の表明であり、また、その人の態度そのものであるともいえる。だからその点では、「~も」であろうと「~しか」であろうと、単に「375㎖ 残っている」も、いわば同じだ。言い方をかえれば、言語化することで人は事態の存在なり認識なりを担保しているし、話し手である自分が聞き手ともなって、再認知するという構造をもっている。
世の中のモノ、コト、ココロ——それらを言語化することで、人は意味付け、価値付けをするわけだが、我が視界から述べるそれは、あたかも対象を客観的に描いているようにみえて、実は、主観的な表明でもあり、いわば己が己に聞かせる文章、ひいては物語ともなっている。記述した事態を繋げ、ひとつづきにして語るというのは、古今東西人間が繰り返してきたことだ(シーズン1 第17回 人は世界を「物語」で知る(前編))。
「兄は今日旅立つ。」と「兄は今日旅立つらしい。」は情報の確度が違うと普通説明されるだろう。しかし、発言者が言語化して表明するという点で同じであり、そういう意味では「私」の態度は、「兄は今日旅立つ。」にもしっかり現れている。中学生の国語では、「旅立つらしい」を、「旅立つ/らしい」には切らないというように普通指導する。それは、上に上げた例文の「旅立つ。」と「旅立つらしい。」を比べたときに、いずれにも話し手の態度、大げさにいえば話し手からみる世界がある、と考えれば納得できることであるだろう。ただし、日本語学の歴史では、別の考え方もあるのだが(たとえば時枝誠記による説)、それはまた機会を改めよう。
「客観」とは何なのか、いや、私たちが「客観」とみなしているのは何なのか。そこには必ず、言語がかかわっているのである。
著者紹介
尾山 慎(おやま しん)
奈良女子大学教授。真言宗御室派寳珠院住職。
著作に『二合仮名の研究』(和泉書院、2019)、『上代日本語表記論の構想』(花鳥社、2021)、『日本語の文字と表記 学びとその方法』(花鳥社、2022)。
今回よりシーズン2として再開しました。
また人文科学のみならず、自然科学、宗教にまで足場を広げつつ、様々な話題に触れたいと思います。
引き続き、よろしくお願いします。