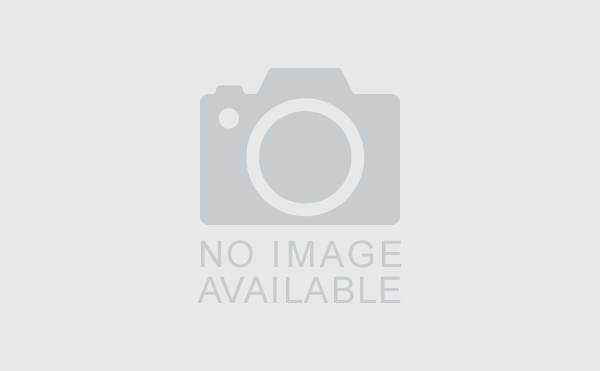シーズン2 第5回
「文学」を考える(後編)
尾山 慎

シーズン2がスタートしました!
文学は〝役にたたない〟のか?
学校教育について「文学を教えるくらいなら、株の取引方法でも教えたらどうか」などという声を耳にする(目にする)機会が、近時ときどきある。「実学志向」と称して、教育の現場から文学や哲学などを追い出そうとする空気はたしかにあって、グローバル競争、データ駆動型社会、キャリア教育の文脈では、即戦力の知識、実学の装備——さもありなん、というところではある。しかし、筆者は個人的になぜ、文学と〝引き換え〟にしないといけないのかよくわからない。文学教育に加えて、株投資の実学も教えるのなら理解できるのだが。単に文学を追い出したいだけの口実なんじゃないかと邪推してしまう。
たしかに、文学を学んだからといって即座に家計が潤うわけではない。詩を暗唱できることが給与明細に反映されることもない。けれど、そうした「目にみえる即効性」の有無が教育の価値を定める唯一の物差しとみるのは、やはり浅薄だといわねばならない。
たとえば、株取引に必要なのは情報処理力、判断力、あるいはリスク管理の感覚だろう。しかし、「何をリスクとみなすのか」「どのような価値に投資するのか」を決めるのは、結局のところ人間の価値観そのものであるはずだ。そしてその価値観とは、単なる経済モデルだけなのではなく、物語や歴史、倫理や想像力といった非数値的な「読む力」「感じる力」に根ざしているとおもうのだ。
文学はたしかに「役にたたない」かもしれない。だが、そもそも「文学」は「役にたつ」という概念そのものを再定義する装置であるとおもう。文学は、〝役立つや否や〟一辺倒の社会に対して、「そもそも〝生きるに値する人生〟とは何か?」などと問い返す最後の知的防壁なのだ。そして前編で定義したとおり、そうした個々人の開かれた解釈行為をもって立ち上がってくる表現体(ことば、文章を代表として、絵画、音楽など)を、「文学」と呼んでみたい、ということであった。
読む行為がもたらすもの
文学は「他者理解の訓練装置」でもある。他人の人生を仮想的に追体験することで、読者は自らの枠組みを越えた共感と想像力を養うことができる。文学的フィクションの読解は、そうした疑似体験を通して他者への共感能力を高める効果がある(シーズン1 第17・18回参照)。ここで重要なのは、物語が単に「内容を知る」ものではなく、読者の内面に「他者の視点を仮想的に宿らせる」過程であるという点である。
また、文学は歴史の「情動のアーカイブ」としての機能も果たす。アーカイブとは古い記録を長期的にわたって保管しておく書庫や公文書館のことだ。これに喩えてみよう。法制度や年表がとらえきれない時代の「空気」や「感情の記憶」を、物語は、刻み込む。レマルク『西部戦線異状なし』がそうであるように、一兵士の視点から描かれた戦争体験は、数値化不能な歴史の実感を提供することがある。これは、文学が「感情の歴史」を記録するメディアでもあることを示すだろう。このように文学は、認知・倫理・記憶の領域において、人類が他者とつながり、過去を感受し、内面を豊かにするための不可欠な文化的装置となっているのである(なので、価値がない、というのは、価値に気づいていないだけだ、といっておきたいとおもう)。
ことば・社会・思考をつくりかえる力
文学は単なることばの連なりではない。それはことばの力をもって、社会の構造や人間の思考様式を、常に刷新する力を秘めている。たとえば、言論統制や情報統制がなされる社会があったとする。文学はそこで、比喩や寓意という表現を通じて、直接的に語れない真実を浮かび上がらせることができるだろう。あるいは体制批判を物語のなかに封じ込め、フィクションを通じて言語化することで、民衆の沈黙に〝声〟を与えることができる。こうした機能は、文学が政治体制の管理下の外にある装置として働く証となるだろう。
さらに文学は、言語そのものの再編や更新を促す。文学はまさに「新たな語りの地平」を切り開く発明行為でもある。語彙を拡張し、比喩を創出し、思考の枠組みを組み替えるという、極めて生産的な文化実践なのである。
普遍性と虚構の力
文学はまた、普遍的な共有財でもある。文学は、言語・宗教・国家・時代を超えて受容されてきた。アンネ・フランクの『日記』が世界中で読まれ続けるのは、単なる戦時下の記録だからではない。そこには、生きることへの恐れや希望、家族への愛、アイデンティティの不安といった、文化を超えて共鳴する「人間の根源的経験」が描かれているからである。ことばの「虚構を共有する能力」(シーズン1 第12回参照)のなかでも、とりわけ「文学」は最も洗練された表現形態である。ユヴァル・ノア・ハラリは『サピエンス全史』(河出書房新社、2016)において、人類が大規模な社会を築けたのは、宗教や国家といった〝虚構〟を信じ合える能力に依るとしたが、「文学」は、まさにこの能力の進化上における重要な存在である。神話や叙事詩は共同体の規範を物語化し、集団内での協調と共通理解を可能にした。現代の小説や詩もまた、形を変えつつ今日その役割を担っている。さらには、文学は「未来を構想する実験装置」でもある。SF やユートピア文学は、制度や社会設計の思考実験を提供し、現実の枠を超えて「ありうる世界」のビジョンを提示する。ここにおいて文学は、制度的・科学的創造の母胎ともなりうるのである。
「生きる知」としての装置
ここまでみてきたように、文学の意義は単なる娯楽や文化資産にとどまらない。それは、共感の訓練であり、記憶の継承であり、批評と想像の空間であり、進化と創造の基盤である。現代社会において、テクノロジーが進展し、情報が過剰に流通する一方で、深い対話や想像力、倫理的な思考がしばしば後景に退いているところがないだろうか。そうした時代だからこそ、文学はますます不可欠な意味をもつ。文学は、私たちが「人間であること」を問い直すための装置であり、他者と共に生きることの複雑さや豊かさを見失わないための〝読み書きの知〟だといえよう。だから、私たちの生きる空間、教育現場から追い出してしまうなんて全くとんでもない話なのである。文学は「生きることの意味を問い続け、そして更新し続ける技術」なのだから。
遅効性だからこそ気づきにくい
文学の忌避、排除は、学ばなくなっても〝今すぐに困らない〟ことを理由にした安易な発想であり、実際は未来の根幹を削ってしまうのではないか。文学というのは、今日読まれなくても、明日教えられなくても、学校の授業から消えたとしても、社会はかわらずきっと回るだろう。ニュースは流れ、経済は動き、メールは届く。だが、それがいかにも〝問題ないようにみえる〟ことこそが、実は深刻な兆候なのだ。
「文学」の効果は、ありきたりな言い方だが、遅効性である。土のなかに仕込まれた種のように、すぐには芽を出さないが、気づけば根を張っている。逆にいえば、「文学」を切り捨てても社会はすぐに瓦解するわけではない。だからこそ、ときに〝不要〟と錯覚する。車の車輪を一つ外せばすぐに停止するしかないが、倫理や共感、想像力といったこれまで長年〝文学が培ってきたもの〟を外しても、社会は惰性でしばらくは進むことだろう。この〝惰性である程度はいく〟というのが怖い。だから大切であることに気づかないのだ。
文学を忘れた社会がここにあるとしよう。ますます「自分にとって意味があるかどうか」、功利でしか測れない社会に変貌するしかない。損得、効率、即応性といった尺度しか通用しない世界は、共感のゆらぎや、他者の苦しみに寄り添う〝非合理〟を、どんどん追い出してしまうことだろう。
古典をはじめとするような文学不要論は、要するに「人類の知的貯金を食いつぶしても、まだ残高があるうちは大丈夫」といったような、楽観的な怠慢だとおもう。ある意味、贅沢な時代の特権的な脳天気さといえるかもしれない。だが、だからこそ、まさに今この世にこそ、文学は、そうした「鈍さ」に対する警鐘であり続ける必要がある。
いま問うべきは、「文学は何の役にたつのか」ではない。「文学なしで人間性は保たれるのか」ではないだろうか。
著者紹介
尾山 慎(おやま しん)
奈良女子大学教授。真言宗御室派寳珠院住職。
著作に『二合仮名の研究』(和泉書院、2019)、『上代日本語表記論の構想』(花鳥社、2021)、『日本語の文字と表記 学びとその方法』(花鳥社、2022)。
![]() シーズン2 第6回 漢字廃止へのまなざし——文字とことばの「国際化」とは(前編)
シーズン2 第6回 漢字廃止へのまなざし——文字とことばの「国際化」とは(前編)
![]() シーズン2 第4回 「文学」を考える(前編)
シーズン2 第4回 「文学」を考える(前編)