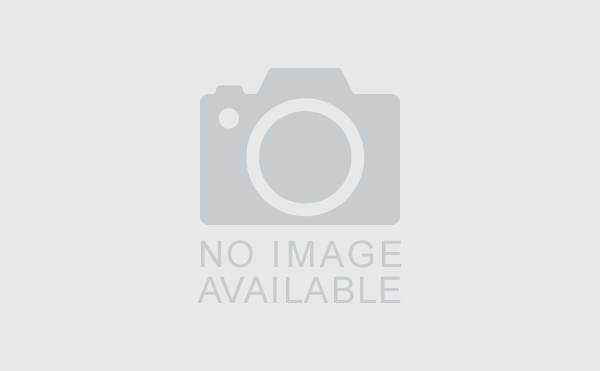シーズン2 第8回
漢字廃止へのまなざし
——文字とことばの「国際化」とは(後編)
尾山 慎

コラム延長戦!「文字の窓 ことばの景色」。
やさしい言い換え、やさしい表記の功罪
以前、「清拭」と「体を拭くこと」という言い換えについて触れたことがあるが(シーズン1 第16回)。かんたんに言い換えた介護や医療用語しか理解できない人が、旧来の専門用語で指示を出されてしまうことがあったら、とても困ったことになるだろう。そんなことは指示を出す側の人が気をつければ良いのかもしれないが、それこそ決して簡単なことではないと思う。現場は日々、走っているのだ。語学の教室ではない(しかも、そういう配慮的な語の選択ができるとしても、「指示を出す人」側の気苦労への顧慮もあってしかるべきである)。ここに横たわるのは〝過渡期の犠牲者たち〟だ。そうでなくてもことばは少しずつ変わっていっているが、何かを変更しようという人為的操作を加えるとしても、ことばというのはある日突然、プログラムを入れ替えるように、〝総とっかえ〟はできない。新しい言い回しを導入するにしても、旧来のことばも併存する中で皆やっていかねばならないのだ。

(画像は生成 AI による)
ここで生じる軋轢を、「致し方ない」「やむない」だけで済ませて良いものだろうか。「ノイラートの船」というたとえがあるが(シーズン1 第23回)、我々は、船にのって航海しつつ、その船の修理、増築を同時に、絶え間なく行ってもいる。だから、ある意味では常に「過渡期」なのであるが、その「過渡期」を可能な限り軋轢や齟齬が生じないものとして航海していきたいものだ。
漢字をやめる議論をするとき、ついつい、「完全に漢字がなくなった世界」ばかりを想像してその成否が語られがちだが、「変更の過渡期」こそが、真に議論の対象なのではないかと思う。仮に、漢字教育を来年からやめると決めたとしても、今後数十年にわたって、習った世代と習っていない世代は、同じこの社会で共存していかねばならない。それは果たしてどういう社会なのか。あらゆる可能性が考察されるべきだろう(筆者の試算では、誰もが1文字も習わず、必然的に誰ももう漢字を書かないし、読めないし、過去の文献類以外は社会にも存在しないという無漢字社会に完全に移行するには少なくとも半世紀~70年はかかるとみている。詳細は『日本語の文字と表記』)。全員が漢字を捨て去った世界を想像するその前に、まずその長きにわたる過渡期、移行期の実態を考え、話し合わなくてはならない。
漢字という〝膨大で面倒なもの〟を減らす、廃止する——しかし、不均衡や格差をなくそうと試みたことが、格差を助長するという矛盾を孕んだリスクを生んではなにもならないだろう。漢字や漢語も、「やさしさ」を誰のために、どの次元のどの規模で提供するのか、いつも、目配りが大切だ。
「国際化」というマジックワード
シーズン1 第16回「現代日本語ローマ字事情」でも「国際」って何なのか、と述べた。「国際化」——今風で、現代社会を生きるキーワードであることには違いない。筆者もそのことは否定しない。鎖国など、200年以上前だからできたことであって、いまや諸外国との関係なしに、日本という国の存続は考えられない。ということで、「国際化」とは、いかにも現代という時代に即していて、未来に開かれていて、進歩的な印象をもつことばとなっている。だがこのことば、実は結構都合のよい、魔法のようなところがある。たとえば、あるプロジェクトで A・B の2案が競っているとき、「国際化のために A 案を採用」などと主張すると、なんだかそれだけでもう対峙する B 案を封じる力を持ちうる。とくに B 案が国内向けの案だとしたらなおさらだ。なぜなら A 案に反対する B 案の人には、「ああそう、じゃあ国際化しなくていいって言うんだね?このご時世に?」などとすり替えて攻めうるという圧を伴うからだ(当然このロジックはズルいのだが)。国際化=正という印籠にできてしまう怖さがある。そしてそもそも今日言う「国際」とは、多くの場合「欧米」のことを指しているであろう点も非常に気になるところだ。「マジック」と言ったのはこの「コクサイ」ということばのつかみ所のなさにある。つかみ所のないことばは普通使いにくいのだが、他方、伸縮自在、変幻自在の魔術にもなり得るのだ。
たとえばまさにその、漢字。「日本語の国際化の妨げになる」といった主張がある。しかし、漢字は中国、韓国、そして日本で広く用いられている。歴史的にみても、東アジアに広範に広がり、現在の世界人口で見ても、十数億に達する。漢字のどこが「非国際的」なのだろうか、と筆者は常々思っている。きっと答えは簡単で、そういうときの「国際」の基準はアルファベット文化圏、多くは欧米なのであろう。
国際化のために漢字は減らすべき、はやはりどこかおかしいと思う。単に非漢字圏言語への迎合になってしまわないか。使いこなすには確かにかなりの学習が必要だが、そのまま「非効率」、しかも、「だからやめよう」と、単線的に話のステップを運んでいくのは、どうにも賛成できない。前編でも触れたとおり、文字には、制度的側面と文化的側面がある。制度的には面倒な面はあっても、文化的側面をやはり無視するわけにはいかない。それに、制度だとしても、日本「語」と日本語の「文字」は別だが、しかし、複雑な末梢神経のように両者は関連し合っている。テープカットするように一カ所だけ切れば切り離せるというものではない。漢字が日本語を成り立たせている面は、かなりあるので、文字だけ変更すればいいというわけには、なかなかいかない。結局、日本語をどうするのかという議論に必ずなるし、言い方を変えれば〝日本語そのもののことはおいておいて、文字表記だけ変更〟という単純化はできないのである。
漢字をめぐって、合理性と効率だけで続けるかやめるか決めうるものではない(もちろん、文化的側面を錦の御旗にして、制度的側面を全く振り返らないことがあってもいけないが)。常用漢字約2100という枠組みは、文化と制度を両方見据えた結果であり、今後も皆で揉んでいくべきものであろう。常に、継続審議課題であるということについては賛成である。次節にいうように、この20数年で漢字を取り巻く状況は大きく変わった。それを視野にいれた議論でなくてはならない。
代わりに読み書きしてくれる新たなる「相棒」の登場
漢字制限論、漢字廃止論が、多く「国際化の弊害」「学習上の負担」「多様で複雑な表記の不合理」ということをキーワードに論陣を張ってきたが、この20数年で大きく状況は変わった。いいかえれば20世紀以前に、制限、廃止論者が危惧していたこと——膨大な記憶負担、送り仮名の是非、難漢字の読み書きといった日本語表記の多様性がもたらす特有の〝圧〟についてなど——が変貌しつつあるということだ。それは、電子機器、AI の存在である。スマホという手のひらサイズ PC と、そこにいまや生成 AI の存在によって、制限、廃止論者がリスクに掲げてきたことを、かなりの面で克服したりサポートしたりできる状況にある。少なくとも漢字で書かれたものを読むということのハードルは、明らかに下がった。異言語のアクセスにしてもそうである。中編でアラビア語を例にしたが、あの例文は翻訳アプリにかけて、さらに chatGPT に助言をもらった。もしこれを手作業、つまり紙媒体の辞書を片手にカタカナへの置き換えを思案するとなると、日本語で読めるアラビア語の辞書は持っていないのでたぶん、図書館にいって、なんだかんだであの短い一文で2時間ほどはかかっただろうと思う。アラビア語作文なんてしたことがないので(当然、文字も手で書いたことがない)、もっとかかるかもしれない。自宅から図書館への行きかえり含めるときっちり半日仕事だ。あきらめて例文は英語にしておこうかなどとくじけたりしたかもしれない。実際は、3種類ほどの翻訳アプリにかけて確認し、それを AI に検証してもらって、カタカナ表記を考案させ、さらに表記の開始箇所を左右反転させる(これが手打ちだとかなり骨が折れる)ところまで含めて、5分かからなかった。キーボードで日本語を打ち込んだ後の5分弱の間、動いていたのはマウスを握る右手、二本の指だけだ。こういう状況は20世紀に漢字制限論、廃止論が議論されているときにはおそらくほとんど想像がつかなかったことである。あるいは当時、機械翻訳の精度はまだまだで、信頼がおけるものではなかっただろう。しかしいまや、漢字を一文字も読み書きできない外国人が、日本語の本一冊まるごとを、ものの1分もかからずに AI に翻訳させて、読めてしまう時代なのである。またその感想を漢字かな交じりのメールとして書いて、日本語話者に送ることもできてしまう(いま生成 AI の書く手紙、メールの文面は相当に自然になっている。AI が書いたと見抜くのが難しいことも)。2025年の今、電子機器、AI の進歩で、漢字廃止論は、まったく別の方向から、大きな見直しを迫られている。
そもそも、廃止といっても人類全員で一斉に忘却するわけではない(そんなことはできない)。JIS コードをある日から廃絶するわけでもない。本屋の本を全部焼却することもできない。ということはつまり、現状のままで、身の回りの機械をより活用するという時代が来ているということだ。だからといって、もう漢字をめぐる問題は万事、今後とももう何も考えなくていいわけではもちろんない(災害時のやさしい日本語、基礎的な漢字に限る表記などは依然として重要)が、いま私が、あなたが、あの人が手にもっているその〝小さな機械の頭脳〟が、まだなかった時代に交わされていた議論からは、大きく転換するときに、もうきている。
洗濯板で手で洗濯をしていた時代にあったであろう様々な問題は、洗濯機なるものがでてきたことによって、その問題のいくつかがなくなり(解決され)、そして洗濯機だからこそ新たな問題がでてきたはずだ。そしてもう一つ、機械にやらせて、洗濯板を使って手で洗濯しないなんて怠惰だ,堕落だなんてもう誰も言わないだろう。こういった、時代、社会に即した、議論すべき観点そのものの振り分け、見極めをする必要がある。今後の漢字社会論は、政策、教育と連携しつつ、常に、電子機器と AI をも含めた、常時継続審議の議論であるべきだろう。
著者紹介
尾山 慎(おやま しん)
奈良女子大学教授。真言宗御室派寳珠院住職。
著作に『二合仮名の研究』(和泉書院、2019)、『上代日本語表記論の構想』(花鳥社、2021)、『日本語の文字と表記 学びとその方法』(花鳥社、2022)。